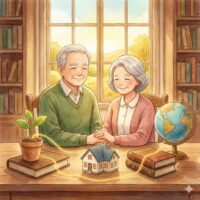
「夫婦で悠々自適の生活を送っているけれど、実は『死んだ後』のことが一番心配なんです」
先日、資産運用のアドバイスをさせていただいている70代のご夫婦(I様)から、こんなご相談をいただきました。
I様ご夫婦は、先祖代々の土地にアパート2棟を所有し、奥様もご実家の相続資産をお持ちの、いわゆる「準富裕層」です。お子様はいらっしゃいません。
傍から見れば、経済的な不安など皆無に見えるお二人。
しかし、お子様のいないご夫婦(DINKS)だからこそ抱える、特有の「深い悩み」がありました。
この記事では、実際にあったご相談(※プライバシー保護のため一部設定を変更しています)を元に、**「子供のいないご夫婦が直面する相続の落とし穴」と、I様が選ばれた「賢い出口戦略(遺贈・任意後見)」**について解説します。
目次
I様のご主人の一番の悩み。それは**「兄弟との不仲」**でした。
「先祖代々の土地を守ってきたのは私だ。それなのに、私が死んだら、疎遠で仲の悪い兄弟たちに権利がいってしまうのか?」
「妻と兄弟たちが、遺産分割の話し合いをするなんて想像しただけでも恐ろしい」
お子様がいない場合、相続権はどうなるかご存じでしょうか?
第一順位の「子」がおらず、第二順位の「親」もすでに他界している場合、相続権は**「配偶者」と「兄弟姉妹」**に移ります。
もし遺言書がなければ、残された奥様は、ご主人の兄弟たち(義理の兄弟)全員の実印と印鑑証明書を集めなければ、銀行預金ひとつ解約できず、不動産の名義変更もできません。
想像してみてください。
最愛の夫を亡くした悲しみの中で、普段付き合いのない、しかも夫が嫌っていた兄弟たちに頭を下げて「ハンコをください」と頼む姿を。
中には「ハンコ代」として高額な代償金を要求されるケースも珍しくありません。
I様は「それだけは絶対に妻にさせたくない」と強く決意されていました。
もう一つの不安は、生前の管理です。
特にI様のように不動産(アパート)をお持ちの場合、リスクは深刻です。
「もし私が認知症になったら、アパートの修繕や契約更新は誰がやるんだ?」
「妻が先に逝って私が一人になったら、誰が私の面倒を見てくれるんだ?」
お子様がいれば、実質的に財産管理を任せることもできますが、お子様のいないご夫婦の場合、頼れる身内がいないケースが多々あります。
資産はあるのに、認知症で口座が凍結され、アパートの大規模修繕もできず、ご自身の介護費用すら引き出せない…。
これが**「資産凍結」のリスク**です。
お金があることと、お金を使えることは別問題なのです。
これらの不安を解消するために、I様ご夫婦と私(FP)が二人三脚で作り上げた「出口戦略」の一つ目が、**「公正証書遺言」**です。
ここで、FPとして最も重要なポイントをお伝えします。
それは、**「兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)がない」**という事実です。
最低限保障された相続の取り分です。子供や親にはありますが、兄弟にはありません。
つまり、遺言書に**「全財産を妻に相続させる」とたった一行書いておけば、不仲な兄弟に財産が渡るのを100%防ぐことができる**のです。兄弟から「俺にもよこせ」と言われる法的根拠はゼロになります。
この事実をお伝えした時、I様の表情が一気に明るくなりました。
「なんだ、紙一枚で解決できることだったのか」と。 ただ、I様が本当に安堵されたのは、遺言書ができたこと自体ではありません。 私が間に入り、「長年言えなかった『俺が死んだら頼むな』という言葉を、奥様に伝えられたこと」。 法的な書類作成だけでなく、この**「夫婦の想いのすり合わせ」に立ち会うこと**こそが、私がFPとして最も大切にしている役割です。
次に、認知症リスクへの備えとして導入したのが**「任意後見契約」と「財産管理委任契約」**です。
これは、簡単に言えば**「元気なうちに、将来の代理人を自分で決めておく契約」**です。
I様ご夫婦は、まず「お互い」を後見人に指定しました。
しかし、老々介護のリスクや、二人が同時に倒れた場合に備え、信頼できる専門家(司法書士や法人)を「予備的な後見人」として設定する準備も進められています。
これで、いつ何があってもアパート経営や生活費の支払いが止まることはありません。
行政書士や司法書士と連携し、法的な後ろ盾を作っておくことが、資産家の責務とも言えます。
さらにI様は、奥様も亡くなった後の「その先」まで考えられました。
「妻も亡くなった後、私たちの財産はどうなる?」
「遠い親戚にいくか、国庫(国)に没収されるだけなら、社会のために使いたい」
そこで、最終的な資産の行き先を、お二人が関心のある医療研究機関や育英会へ寄付する**「遺贈(いぞう)」**の準備も組み込みました。
自分の死後、資産がどう使われるかを自分で決める。
これにより、資産は単なる「残り物」から、**未来の社会を育てる「生きた証」**へと変わりました。 自分の資産で、未来の誰かが笑顔になる。 それは、お子様がいないご夫婦だけに許された、究極の「親心」の形なのかもしれません。
「対策を始めたら、不思議と夫婦の会話が増えて、これからの旅行がもっと楽しみになりました」
一連の対策を終えた後の、I様ご夫婦の晴れやかな笑顔が印象的でした。
お金や不動産は、あるだけでは安心できません。
特に、お子様のいないご夫婦にとって、以下の3つを決めることは急務です。
この3つが決まった時、初めて資産は「不安の種」から「人生を最後まで楽しむための翼」に変わります。
「うちはどうだろう?」と思われた方。
元気な今こそ、貴方の資産の「出口」を一緒に考えませんか?
お子様がいないからこそできる、自由で賢い設計図を、FPとしてご提案いたします。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム