「相続・贈与」では、相続税対策や遺言書の準備、生前贈与や遺産分割のポイントをわかりやすく解説し、円満な相続と資産承継をサポートします。

親の介護が必要になったとき、多くの家庭では「どの財産を介護費用に充てるのか」「相続のために何を残すのか」という難しい判断に直面します。介護費用は平均で数百万円から1,000万円以上かかるケースもあり、その支払い方次第で、将来の相続財産の形が大きく変わります。現金や預貯金を取り崩すのか、不動産を売却して資金を確保するのか、それとも生命保険を活用するのか――。使う財産と残す財産の選択を誤ると、介護中の…
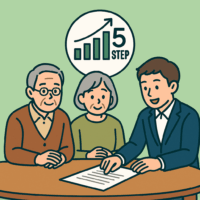
「相続なんてまだ先の話」と思っていませんか? しかし、家庭裁判所で扱われる遺産分割トラブルのうち、約8割は「遺産5,000万円以下の一般的な家庭」で発生しています(司法統計年報より)。 また、民間調査でも相続経験者の約2〜3割が何らかのトラブルを経験しており、決して他人事ではありません。 相続対策は、“親が元気なうち”だからこそできる家族のプロジェクトです。 準備を後回しにすると、認知症の発症や突…

相続に関する悩みは、税金だけでなく「誰にどう分けるか」「家族が揉めないか」など多岐にわたります。 特に不動産中心の資産構成では、分割の難しさや納税資金の確保が大きな課題となります。 「うちは仲が良いから大丈夫」 「まだ元気だから先の話」 そう思っている方ほど、いざという時に「争族(そうぞく)」に巻き込まれやすいのが現実です。 問題を未然に防ぐには、目先の節税策に頼る「相続対策(点)」ではなく、家族…

【警告】「節税」目的の法人化は失敗する?不動産オーナーの手取りが減る罠 「年間の家賃収入が増えてきたから、そろそろ法人化した方が税金が安くなりますよ」 顧問税理士さんからそうアドバイスを受けて、「それなら会社を作ろうか」と私のところへ相談に来られる不動産オーナー様がよくいらっしゃいます。 しかし、ライフプランのシミュレーションを行った結果、私はしばしばこうお伝えします。 「〇〇さんの場合、法人化は…

相続が発生すると、短期間で多くの手続きを進めなければならず、期限を過ぎると大きなデメリットが発生することもあります。特に「7日」「3か月」「10か月」など、重要な期限ごとに適切な行動を取らなければなりません。本記事では、相続手続きの全体像を時系列で整理し、相続放棄や遺産分割、相続税申告などの重要な流れと注意点を分かりやすく解説します。 相続手続きはなぜ大変?全体像を理解することの重要…

昨今遺贈寄付という言葉を 良く耳にするようになってきました。 その関心の高まりにあわせて 今回は遺贈寄付のことについて その進め方 と メリット、デメリット について まとめてみました。 1,遺贈寄付とは 遺贈寄付とは、個人が遺言によって遺産の全部、 または一部を公益法人や自治体、NPO法人、学校法人、 などの公益団体に寄付をすることをいいま…

「相続税対策でアパートを建てませんか?」 そんな営業トークを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 確かに不動産を活用すれば、現金をそのまま持つよりも相続税評価額を大きく下げることが可能です。しかし、「税金が安くなること」と「家族が幸せになること」はイコールではありません。 無理な借金をして節税には成功したけれど、その後の返済で老後資金が枯渇したり、流動性の低い不動産を残された家族が分割で…

年齢を重ねるにつれて、「もし認知症になったら」「自分の財産はどうなるのだろう」と不安を感じる方が増えています。実は、判断能力が低下すると預金の引き出しや不動産の売却といった“日常の手続き”さえできなくなることがあります。その備えとして活用できるのが、「法定後見」「任意後見」「家族信託」の3つの制度です。 これらはいずれも「将来への備え」という点では共通していますが、目的・仕組み・使うタイミングが大…
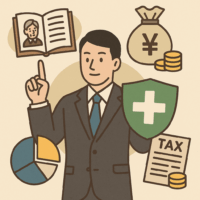
「孫が生まれたので、お祝いに学資保険に入ってあげたいんです」 「将来の大学費用の足しになるように、今のうちに300万円くらい贈与しようかと…」 50代・60代のご相談者様から、このような温かいご相談をいただく機会が増えました。 かわいいお孫さんのために何かしてあげたい。そのお気持ち、とてもよく分かります。 しかし、FPとして、時には心を鬼にしてこうお伝えすることがあります。 「今の時代、学資保険だ…

相続対策というと「子供への分配」や「節税」ばかりに注目しがちですが、最も守るべきは**「残される配偶者(妻や夫)の生活」**です。 日本の法律では、配偶者は相続において非常に優遇されています。 しかし、「税金がかからないから」といって安易に「全財産を配偶者に」と決めてしまうと、かえって将来の税負担が増えたり(二次相続)、手元の現金が不足して「資産はあるのに生活費が足りない」という事態に陥ることがあ…
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/




