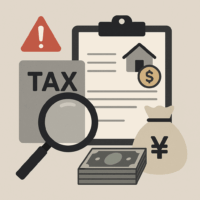
相続税の税務調査は、相続税申告者の約2割に実施されるといわれています。
調査が入ると聞くと不安を感じる方も多いですが、調査の仕組みや対象となりやすいケースを理解していれば、必要以上に恐れることはありません。
本記事では、税務調査が入る確率や時期、調査されやすい7つのパターン、そして事前に行うべき5つの準備を徹底解説します。
生前からの適切な対策と準備を行うことで、相続手続きの不安を減らし、調査への対応力を高めることができます。
目次
相続税の税務調査と聞くと、多くの人が「何か悪いことをしたのでは?」という不安を感じるものです。
しかし、相続税の税務調査は、申告内容に誤りや漏れがないかを確認するために行われる、国税庁の通常業務の一環です。
恐れるべきものではなく、正しい知識と準備があれば冷静に対応できます。特に相続税は財産の種類が多岐にわたるため、評価や申告にミスが起こりやすいのが特徴です。
生前から相続財産を把握し、適切に整理しておくことで、税務調査の対象となるリスクを軽減できます。
全体像を理解することで、不安を解消し、スムーズな相続手続きと節税対策が可能になります。
国税庁が毎年公表する「申告実績の概況」や「相続税の調査状況」によると、相続税の申告件数のうち約2割前後が税務調査の対象となります。
実地調査に加え、文書照会や電話による簡易な調査も含めると、想像以上に多くのケースが確認されています。
調査が入る時期は、相続税の申告期限から1年~2年後の8月から11月が多く、人事異動後に調査体制が整うためとされています。
さらに、税務署は年明けから所得税の確定申告業務が繁忙期となるため、相続税調査は年内で完了させたいという意向が強いのも特徴です。期間としては、個人事業主の場合で1~2か月、法人では2~3か月程度が目安です。
こうした傾向を知ることで、事前に資料や書類を整え、調査に備える準備ができます。
税務調査には特定の傾向があり、次の7つのケースは特に対象となりやすいといわれています。
1. 税理士に依頼せず自己申告している場合
計算ミスや財産の見落としが起こりやすく、税務署も重点的にチェックします。
2. 遺産総額が2億円を超えるケース
財産の評価が複雑になるため調査対象になりやすい傾向があります。
3. 生前の入出金が多い場合
特に使途不明な大口出金は詳細に調査されます。
4. 収入に比べ申告財産が少ない
バランスの不整合から調査対象になりやすいです。
5. 家族の資産が多い場合
相続税対策のための生前贈与が疑われます。
6. 海外資産を保有している場合
申告漏れのリスクが高い傾向にあるため。
7. 相続直前に不動産購入などの節税対策を行った場合
これらに該当する場合は特に事前準備が必要となります。
税務調査を恐れず、正しく申告するためには5つの準備が効果的です。
1. 税理士に依頼する:プロが申告することで、署名による信頼性が高まり調査リスクが低下します。
2. 財産・債務の正確な把握:相続財産を家族全員が明確に理解し、漏れのない申告を心掛けましょう。
3. 生前贈与の証拠を残す:契約書や銀行振込記録を必ず残しておくことで、贈与を明確に証明できます。
4. 不明な入出金を整理:特に50万円以上の入出金にはメモや証拠を残すことが重要です。
5. 名義預金や生命保険を精査:名義預金や名義保険は調査対象になりやすいので、事前に洗い出しておくべきです。
これらを徹底することで、調査に入られたとしても安心して対応できる体制が整います。
相続税調査では、特に「名義預金」と「名義保険」がよく指摘されるポイントです。名義預金とは、被相続人が孫や子の名義で貯蓄していた預金のことで、実質的には被相続人の財産と見なされます。これを申告しなかった場合、追徴課税の対象となる可能性が高まります。また、生命保険の契約者や保険料負担者と受取人が異なる場合には、課税対象となる場合があるため注意が必要です。
さらに、現金での贈与やタンス預金も税務署が見抜くケースが多く、隠しきれるものではありません。税務署は預金口座の取引履歴や不動産、株式の売却情報を網羅的に把握しているため、証拠を整備して透明性の高い申告をすることが何よりの防御策になります。
相続税の税務調査は全申告件数の2割程度で行われますが、対策を行っていれば過剰に恐れる必要はありません。
重要なのは、被相続人の財産全体を正確に把握し、書類や証拠をきちんと整えて申告することです。
また、税務調査が想定される資産規模やケースに該当する場合は、税理士に依頼して信頼性を高めることが賢明です。
さらに、家族全員で生前の財産状況や遺産分割方針を話し合っておくことで、相続後のトラブルや申告漏れを未然に防ぐことができます。現代では、タンス預金や現金贈与で隠し通せることはほぼなく、国税庁の調査力は非常に高いと考えてよいでしょう。
事前にしっかりと準備することで、税務調査があっても安心して対応できる体制が整います。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム