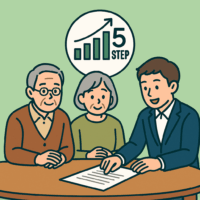
「相続なんてまだ先の話」と思っていませんか?
しかし、家庭裁判所で扱われる遺産分割トラブルのうち、約8割は「遺産5,000万円以下の一般的な家庭」で発生しています(司法統計年報より)。
また、民間調査でも相続経験者の約2〜3割が何らかのトラブルを経験しており、決して他人事ではありません。
相続対策は、“親が元気なうち”だからこそできる家族のプロジェクトです。
準備を後回しにすると、認知症の発症や突然の病気により、資産管理や遺言作成ができなくなるリスクもあります。
本記事では、相続専門のFPが教える「失敗しない相続対策の5ステップ」をわかりやすく解説。
資産の棚卸し、親の想いの確認、相続税・不動産のシミュレーション、遺言・家族信託の活用、そして生前贈与による節税まで。
今から準備を始めれば、「争族」を防ぎ、親の意思を尊重したスムーズな相続が可能になります。
家族の未来を守るために、今すぐ読み始めてください。
目次
相続対策は「親が亡くなってから考えるもの」と思われがちですが、それでは遅すぎるケースも多くあります。
親が元気なうちにこそ、家族で話し合い・準備を進めておくことがスムーズで円満な相続への第一歩です。
親が元気なうちに、意思を確認しながら柔軟な対策を進めることが、家族全員の安心につながります。
相続対策の第一歩は、親の資産と負債の全体像を明確に把握することです。
「なんとなくある」から「明確に把握する」へ。
資産の棚卸しは、相続対策のスタートラインです。
👉 不動産の棚卸しや評価の方法を詳しく知りたい方はこちら
→ 【保存版】シニア世代の不動産戦略|住まい・投資・相続の総合ガイド
相続を円満に進めるには、親の意思と家族の意向を共有することが不可欠です。
想いを確認することは、相続を“争い”ではなく“感謝の継承”にするための鍵となります。
不動産は分けにくく、納税資金の確保も難しいため早めの対策が必要です。
事前シミュレーション=相続の不安を減らす最短ルートです。
相続トラブルの多くは「親の意思が見えないこと」から発生します。
親の明確な意思を法的に残すことで、相続人同士の認識違いや不満を減らし、スムーズな手続きが実現します。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
前者は手軽に作成できますが形式ミスが無効になるリスクがあり、後者は公証人が関与するため信頼性が高く、相続発生後のトラブルを未然に防ぎやすい特徴があります。
👉 認知症対策としての「任意後見制度」や「法定後見制度」との違いを知りたい方はこちら
→ 「法定後見・任意後見・家族信託の違いと選び方|認知症・財産管理の備え方を徹底解説」
早めの準備によって、親の意志を明確にし、家族全員が納得する相続のかたちを整えることが可能になります。
相続税の負担を減らすためには、生前贈与の活用が効果的です。
生前贈与は節税だけでなく、「感謝や想いを伝える家族コミュニケーション」にもつながります。
相続発生時の税負担を抑えるには、「生前贈与」を上手に活用することが効果的です。
👉 どの非課税制度をどう活用すべきかを詳しく知りたい方はこちら
→ 相続対策になる生前贈与の非課税制度7選と活用ポイント
相続対策というと難しいイメージがありますが、実は家族の未来を守るための「思いやり」の行動です。
親が元気なうちに、家族で資産の棚卸しをし、親の想いを確認し、専門家と一緒に課題を整理していくことで、争いやトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書や家族信託で意志を明確にし、生前贈与で資産を移転することは、節税対策であると同時に、家族との絆を深める機会でもあります。
何より重要なのは、「まだ早い」と思って先送りするのではなく、「今だからこそできる準備」に目を向けることです。
相続対策は、親の財産を守るだけでなく、家族全員の安心と信頼関係を築く大切なステップです。
親子で向き合うこの時間が、結果として“親孝行”となり、次世代への思いやりの形になります。
今こそ一歩を踏み出し、将来の安心をともに描いていきましょう。
Q1. 相続対策はいつから始めるべき?
A. 結論は「親が元気なうちに今すぐ」。目安は75歳前後、要介護認定前、物忘れが気になり始める前の段階です。意思確認・資産棚卸し・遺言/信託の整備は早いほど選択肢が広がります。
Q2. 何から手をつければいい?
A. ①資産・負債の棚卸し(一覧化)→②親の想いの確認→③税務・不動産のシミュレーション→④遺言/家族信託の検討→⑤必要書類の整備(通帳・権利証・保険等)の順が基本です。
Q3. 親が話したがらない/きっかけが作れない場合は?
A. 「万一の備えチェック」や通帳・保険の整理など“家事の延長”から始めるとスムーズ。第三者(FP/税理士/公証人)の同席も有効です。
Q4. 家族信託と遺言は何が違う?
A. 遺言は「死後の分配指図」、家族信託は「生前の管理・承継スキーム」。認知症リスクへの備えや不動産の継続管理が必要なら家族信託が有力です。併用するケースも一般的です。
Q5. 家族信託の費用はどれくらい?
A. 信託設計・士業報酬・公正証書作成費用・登記費用などで数十万円~案件規模で変動。信託財産が複数不動産や事業株だと費用は上がります。
Q6. 公正証書遺言にするメリットは?
A. 方式不備リスクの回避、家庭裁判所の検認不要、原本が公証役場保管で紛失しにくい等。相続人間の紛争予防効果が高い点が利点です。
Q7. 生前贈与と相続時精算課税、どちらが有利?
A. 目的・資産の種類・評価額・将来の売却予定で異なります。暦年贈与は柔軟、相続時精算課税はまとまった移転に有効。併用可否や将来の課税影響は専門家と試算を。
Q8. 不動産が主な遺産で分けにくい場合の対処は?
A. 共有・代償分割・換価分割(売却)・生前の資金準備(保険活用)等。小規模宅地等の特例適用可否や納税資金手当てを事前にシミュレーションします。
Q9. 二次相続(もう一方の親が亡くなるとき)も考えるべき?
A. 必須です。一次相続で配偶者に集め過ぎると二次相続の税負担が増えることがあります。一次・二次を通算で設計しましょう。
Q10. まず用意しておくべき書類は?A. 資産一覧、通帳・証券残高、保険証券、不動産登記・固定資産税納税通知書、年金通知、借入明細、家系図(続柄メモ)等。最新化と所在の明確化がポイントです。
*本FAQは一般的情報であり、最適解はご家族の事情で異なります。個別判断は専門家にご相談ください。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム