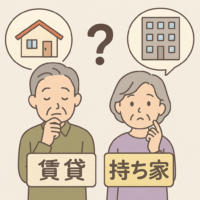
60代を迎えると、「この家に一生住み続けていいのか?」「持ち家を維持するより、賃貸の方が楽では?」といった住まいに関する悩みが増えてきます。
人生100年時代、定年後の暮らしが20年、30年と続く中で、住まいは日々の快適さだけでなく、健康やお金、家族との関係にも大きく影響します。
この記事では、「持ち家と賃貸、それぞれのメリット・デメリット」「住み替えのタイミング」「老後資金とのバランスの取り方」など、60代からの住まい方を徹底解説。
後悔しない選択のために、ライフプランの視点から最適な住まい方を一緒に考えていきましょう。
目次
60代は、これまでの仕事中心の生活から一転し、「自分らしく生きる」ことにシフトしていく大きな転機です。
特に住まいは、生活の基盤であり、安心感や快適さ、将来の不安の有無に直結する重要な要素です。
健康状態の変化、子どもの独立、退職後の収入の減少など、60代以降は生活スタイルが大きく変わるため、これまで住み慣れた家が今後の暮らしに最適とは限りません。
また、老後は「住環境=生活の質」ともいえるほど影響力があり、段差の多い家や郊外の不便な立地に暮らし続けることで、思わぬ孤立や健康リスクを招くこともあります。
将来を見据えて「賃貸か?持ち家か?」を真剣に考えることは、後悔しないセカンドライフを送るための第一歩なのです。
持ち家の主なメリットは以下の通りです。
一方、デメリットも無視できません。
持ち家は「資産」であると同時に、「管理責任」も伴う選択なのです。
賃貸暮らしのメリットは以下の通りです。
デメリットとしては、
賃貸は自由度が高い一方で、将来的な住まい確保に不安が残るケースがあります。
60代から住まいを考える際は、以下の視点が欠かせません。
「住み続けるか、住み替えるか」の選択に正解はありませんが、自分にとって何を優先したいのかを整理することが、最適な住まい選びの第一歩となります。
60代からの住み替えは、老後の生活をより快適で安心なものにするための前向きな選択肢です。
体力や健康状態が比較的安定している今のうちに、将来を見据えた環境へ移ることで、老後の不安を大きく軽減できます。
たとえば、段差のないバリアフリー住宅や、駅・病院・スーパーが近いコンパクトなマンションなどが人気です。
また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やシニア向け賃貸住宅といった選択肢も広がっています。
これらは見守りサービスや食事提供、介護支援などが整っており、一人暮らしや配偶者を亡くした後の生活にも適しています。
住み替えには費用や引っ越しの手間も伴いますが、「今の家にずっと住めるか?」という問いに対して現実的な備えをしておくことで、将来的な住居不安や家族の負担を減らすことができます。
柔軟な発想で住み替えを選ぶことは、60代からの暮らしをより豊かにするカギとなるでしょう。
実際の選択事例を見ることで、自分に合った住まい方のヒントが得られます。
都心郊外の戸建てを売却し、駅近の賃貸マンションに住み替えた60代夫婦は、日々の買い物や通院が格段に楽になり、時間にも心にも余裕ができたと話します。
一方、築30年の持ち家をリフォームして住み続ける選択をした方は、住宅ローンの心配がなく、生活コストを抑えながら安心して老後を過ごせています。
また、子どもが独立したのを機に、地方の実家を相続・改築して二世帯住宅にするというケースもあります。
親の介護や見守りをしながら自分たちの生活空間も確保できるため、家族の支え合いが暮らしの安心につながっています。
このように「賃貸か持ち家か」はライフスタイルや家族関係、資産状況によって最適解が異なります。
大切なのは、自分たちの価値観や将来像に合った住まい方を選ぶことなのです。
60代からの住まい選びでは、「住宅にかかるお金」が老後資金の行方を大きく左右します。
どちらを選ぶにしても、老後の生活費とのバランス、資産の流動性、医療や介護に備える余力が確保できるかをシミュレーションすることが欠かせません。
住まいにかかるコストを「見える化」し、総合的な資金計画を立てることが安心の第一歩です。
60代は、人生の後半をどう過ごすかを見直す重要なタイミングです。
住まいは日々の安心・快適さを左右するだけでなく、老後資金や家族関係にも影響を与える大切な要素です。
「持ち家」か「賃貸」かに明確な正解はありませんが、健康状態、経済状況、家族との関係、そして何より「どんな暮らしをしたいか」という価値観によって最適な選択は変わります。
今後の生活に必要な費用や住環境の変化を想定し、「住み続ける」「住み替える」などの選択肢を現実的に検討することが、安心できるセカンドライフへの第一歩となります。
住まいに関する判断を先送りにせず、今のうちから具体的に準備を始めることで、将来の不安はぐっと軽減できます。
人生100年時代、住まいもまた「ライフプランの一部」です。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム