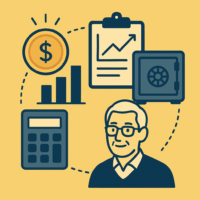
「老後資金のために、NISAで投資を始めなきゃ」
「S&P500やオルカンを買っておけば安心」
50代・60代の相談者様から、このような声を毎日のように聞きます。しかし、FPとしてあえて厳しいことを申し上げます。
「何を買うか(銘柄選び)」だけで安心していませんか?
実は、老後の資産寿命を決めるのは「銘柄」ではなく、「取り崩しの順番」です。
特に恐ろしいのが、リタイア直後の**「株式市場の暴落」**です。
もし、退職して投資生活に入った直後に、リーマンショック級の大暴落が来たらどうなるか。
今回、私が実際に作成したライフプランシミュレーションで検証を行いました。
その結果、ある「仕組み」を持っていたかどうかで、95歳時点の資産に「約7,600万円」もの差がついたのです。
この記事では、衝撃のシミュレーション結果を公開するとともに、暴落から老後資金を守るための**「現金クッション」**という考え方を解説します。
目次
論より証拠です。以下のシミュレーション結果をご覧ください。
【検証モデル】
この厳しい条件下で、2人の人物(AさんとBさん)の資産推移を比較しました。
| 比較項目 | Aさん (暴落時に売った) |
Bさん (売らずに耐えた) |
|---|---|---|
| 95歳時点の残高 | 枯渇寸前 | 余裕あり |
| 資産の差額 | - | 約7,600万円 プラス |
なんと、約7,600万円もの差がつきました。
運用している商品は同じ。市場環境も同じ。
違ったのは、「暴落した時に、資産を売らずに済む現金を持っていたかどうか」。たったこれだけです。
なぜ、これほどの差が開いたのでしょうか?
専門用語では**「収益率配列のリスク(シーケンス・オブ・リターン・リスク)」**と言います。
簡単に言えば、**「資産運用の初期(リタイア直後)に暴落に遭い、そこで資産を取り崩してしまうと、資産寿命が一気に縮む」**という現象です。
株価が50%下がった状態で生活費を引き出すということは、通常の2倍の口数の投資信託を解約しなければならないということです。資産の土台を自ら削ってしまい、その後の株価回復の恩恵を受けられなくなりました。
株価が下がっている間は、投資信託に指一本触れませんでした。手元の現金を使ったのです。そして株価が元に戻り、上昇気流に乗ってから取り崩しを再開しました。これを可能にしたのが**「現金クッション」**です。
50代・60代の資産運用で最もやってはいけないのは、**「生活費のために、暴落した株を売ること」**なのです。
では、Bさんのように資産を守り抜くには、具体的にどうすればいいのでしょうか?
私がFP相談で提案しているのは、以下の3ステップによる仕組みづくりです。
まず、「公的年金(手取り)」と「予想される生活費」の差額を出します。
「そもそも、毎月の生活費や赤字額がいくらか把握できていない…」 という方は、まずは家計の現状整理から始めましょう。基礎的なチェックリストはこちらの記事でまとめています。
▼あわせて読みたい [リンク:資産寿命を伸ばす!50代からの資産管理チェックリスト]
ここが最重要ポイントです。
先ほどの赤字額の「10年分」を、投資には回さず、絶対に減らない「現金(預金・国債など)」で確保します。
これが**「現金クッション」**です。
なぜ10年か? 歴史上、大きな暴落から株価が回復するには5年〜数年かかることが多いからです。10年分の生活費があれば、どんな暴落が来ても「今は売らない」という選択ができ、回復を待つことができます。
「現金クッション」と「直近使う予定のあるお金(リフォーム代など)」を除いた、残りの資金だけを新NISAなどで運用します。
多くの人が失敗するのは、退職金の全額など、手持ち資金のほとんどを投資に回してしまうからです。それでは暴落時に逃げ場がなくなります。
「守り(現金)」と「攻め(投資)」の役割分担こそが、最強の暴落対策です。
「10年分の現金なんて用意できない」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、資産は金融資産(預貯金・株)だけではありません。
ローン返済や豪華な旅行ですぐに使わず、まずは「現金クッション」の構築に充てる。
私たち宅地建物取引士の視点で見れば、持ち家は「巨大な資産の塊」です。
広い自宅を持て余しているなら、売却してコンパクトな住まいに移る(ダウンサイジング)ことで、手元に数千万円の現金を作ることも可能です。
「現金がない」と諦める前に、ご自身の総資産(家・保険・年金)全体を見渡して、組み替えることができないか検討してみてください。
今回のシミュレーション結果は、私自身にとっても衝撃的なものでした。
7,600万円という差は、どんなに優れた投資商品を選んでも埋められるものではありません。
50代・60代がやるべきこと:
「自分の場合は、いくら現金を持っておけばいいのか?」
「自宅を活用してクッションを作るには?」
もし不安を感じられたら、一度具体的なシミュレーションを作成することをお勧めします。数字で未来が見えれば、漠然とした不安は消せます。
暴落は必ず来ます。しかし、準備さえしていれば、それは決して怖いものではありません。
この記事を読んだあなたへ
「現金クッション」の仕組みは分かったけれど、
私の場合は、具体的にいくら確保すればいい?
迷ったら、まずはプロが使う「設計図」を手に入れてください。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム