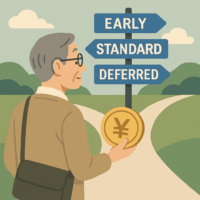
「年金はいつから受け取るのが得なのか?」
50代後半〜60代にかけて、多くの方が必ず直面するテーマです。
年金は原則65歳から受け取りますが、60歳からの繰上げ受給や、70歳までの繰下げ受給も可能です。開始時期によって生涯受給額は数百万円単位で変化するため、判断を誤ると後悔につながりかねません。
FP相談の現場でも「健康」「仕事」「貯蓄」「配偶者の年金」など、人によって最適な選択は異なります。
本記事では、実際の相談傾向やFPの経験をもとに、「繰上げ」「標準」「繰下げ」の3つの戦略をわかりやすく比較。あなたのライフプランに合った“後悔しない選択”を一緒に見つけましょう。
目次
公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は原則65歳開始ですが、実際には前後に幅があり、次の3つから選べます。
ポイント
制度上は75歳まで繰下げ可能ですが、実務では70歳前後が分岐点。65〜70歳の生活費をどう賄うかが現実的な判断材料になります。
| 区分 | 開始年齢 | 増減率 | 一生続く影響 |
|---|---|---|---|
| 繰上げ | 60歳 | −24.0% | 少ない(安心は早い) |
| 繰上げ | 64歳 | −4.8% | 少ない |
| 標準 | 65歳 | ±0% | 基準 |
| 繰下げ | 66歳 | +8.4% | 多い |
| 繰下げ | 70歳 | +42.0% | 多い(長生きほど有利) |
例:基準月額20万円の場合
・60歳開始:20万×(1−0.24)=15.2万円
・64歳開始:20万×(1−0.048)=19.04万円
・66歳開始:20万×(1+0.084)=21.68万円
・70歳開始:20万×(1+0.42)=28.4万円
「片方を標準、片方を繰下げ」にして世帯の底上げ+長寿リスク対策を両立する設計は実務でも多い選択。逆に、無収入期間が長くなる繰下げは、キャッシュ不足で生活の質を落とすなら本末転倒です。
この第1章では“制度の幅”と“増減のロジック”を把握しました。
次章では、**実例ベースで「どんな人がどの戦略に向いているか」**を具体的に見ていきます。
▶関連リンク:年金の繰り下げ受給は何歳までが得?FPが実例で解説する70歳・75歳の判断基準
年金の受け取り方には「繰上げ」「標準」「繰下げ」という3つの方法がありますが、どれが正しいかはその人の状況次第です。
ここでは、実際の相談事例をもとに、典型的な3つのパターンを紹介します。
🔹こんな人に向いている
🔹戦略のポイント
65歳以降も元気に活動できる方にとって、繰下げ受給は老後の後半を支える安定収入源になります。
70歳まで遅らせると年金額は最大42%増額され、これは一生続く仕組みです。
「健康寿命の延び」が進む中、70代後半からの生活費を確保するうえで有効な戦略といえます。
🔹FP現場からの実例
68歳の男性(元公務員)
定年後も顧問として働き、70歳まで繰下げを選択。退職金を5年間で計画的に取り崩し、70歳以降は年金+運用収益で生活を安定化。
「後半の安心を買うつもりで待った」と話されていました。
🔹注意点
▶関連リンク:年金+資産運用で“毎月いくら使えるか”を見える化する方法
🔹こんな人に向いている
🔹戦略のポイント
繰上げ受給は、「早く・確実に」年金を得られる安心感が最大のメリットです。
ただし、1か月早めるごとに0.4%減額され、60歳で始めると最大24%減。
この減額は一生続きます。
長生きするほど受給総額は減りますが、「今を支える」意義は十分あります。
🔹FP現場からの実例
61歳の女性(元パート勤務)
配偶者の年金受給まで2年間の空白があり、生活費確保のため60歳から受給開始。
「毎月の安定収入ができて精神的に楽になった」と話されています。
🔹注意点
FPメモ:
「繰上げ」は損得よりも安心・メンタル安定重視の戦略です。
体調不安や無収入期間が明確な場合は“現金流”を優先するのが正解です。
▶関連リンク:お金を減らさないための“引き出し方戦略”|定年後の取り崩しルール
🔹こんな人に向いている
🔹戦略のポイント
標準の65歳受給は、減額・増額のない中庸な選択です。
「いつから受け取るか」よりも、「年金+αの収入設計」に重点を置き、
・公的年金(定期収入)
・iDeCoや企業年金(補完収入)
・退職金・運用資産(取り崩し資金)
の3本柱で支出のバランスを取ります。
🔹FP現場からの実例
夫65歳・妻63歳のご夫婦
夫婦で標準受給を選び、生活費の約8割を年金でカバー。残りをiDeCo・NISAから補填。
「65歳で一緒にスタートしたことで、家計管理が分かりやすくなった」との声。
🔹注意点
| タイプ | 状況 | おすすめ戦略 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 長寿・健康自信型 | 活動的・資産余裕あり | 繰下げ | 老後後半の生活費を底上げ |
| 健康不安・収入不足型 | 早期退職・無収入期間あり | 繰上げ | 今の安定を優先 |
| 平均的・堅実型 | 健康・生活バランス良好 | 標準 | 安定・計画重視の中庸策 |
💬FPコメント(塩川FP)
現場で多いのは、「一方的に繰下げ推奨」と思い込んで迷うケースです。
でも本質は「どれを選ぶか」ではなく、「どんな暮らし方をしたいか」。
年金戦略は人生戦略の一部。損得より、安心と納得で選ぶのが最良です。
この第2章では、「誰にどの戦略が合うか」を具体的に整理しました。
次章では、より実践的に「年金開始を決める3つの判断軸」を掘り下げます。
年金の繰上げ・繰下げをどう選ぶかは、「損得計算」だけで決めるべきではありません。
FPの現場では、単に「何歳まで生きるか」よりも、**「どんな生き方をしたいか」**を基準に決めた方が後悔が少ないという傾向があります。
そのために押さえておきたいのが、次の3つの判断軸です。
🔹考え方
健康で活動的な人ほど、繰下げ受給が有利です。
70歳開始なら年金額は最大42%増え、その増額は一生続きます。
「何歳まで生きるか」よりも、「何歳まで自立した生活を送れるか(健康寿命)」が判断基準です。
🔹チェックポイント
🔹FPの実例
夫婦ともに健康で登山や旅行を楽しむご夫妻。
70歳繰下げで年金を増額し、「老後後半も自由に動けるうちに使う」と明確な目的を設定。
受給額の増加だけでなく、**“生き方を支える年金”**という発想に転換した好例です。
🔹ワンポイント
🔹考え方
繰下げを選ぶには、65〜70歳の5年間をどう乗り切るかが最大のカギ。
この期間に無収入だと、貯蓄を減らすストレスが大きく、生活の質を落としかねません。
🔹チェックポイント
🔹FP現場からの助言
「繰下げを選びたいが、65歳で無収入になるのが不安」という相談は非常に多いです。
その場合、退職金の一部を“年金の代わり”として5年間に分けて取り崩す設計を行います。
このように、キャッシュフローの“つなぎ設計”ができていれば、繰下げの安心感は格段に上がります。
🔹ワンポイント
🔹考え方
年金は個人単位で受給しますが、設計は夫婦単位で行うのが基本です。
配偶者の受給額・遺族年金・加給年金の有無を踏まえると、タイミングをずらす方が世帯収入が安定するケースが多く見られます。
🔹チェックポイント
🔹FP実例
夫:会社員(65歳退職)/妻:専業主婦
夫は標準65歳受給、妻は70歳まで繰下げ。
妻が長生きした場合も、遺族年金+増額分で安心。
「片方を繰下げ・片方を標準」にすることでリスク分散と心理的安定を両立できました。
🔹ワンポイント
| 判断軸 | 視点 | 合う戦略の傾向 |
|---|---|---|
| 健康状態 | 長寿リスクをどう捉えるか | 長生き自信あり → 繰下げ有利 |
| 資産・収入 | 65〜70歳のつなぎ資金が確保できるか | 余裕あり → 繰下げ / 余裕なし → 標準・繰上げ |
| 家族構成 | 夫婦全体での収入設計 | タイミングをずらす・組み合わせ最適化 |
💬FPコメント
年金の受給は「確率論」ではなく「納得の選択」です。
3つの軸を整理した上で、**“数字よりも安心感”**を基準に決めると、あとで後悔しません。
年金だけにとらわれず、退職金・NISA・不動産収入・介護費用などを含めた「総合老後設計」で考えるのがベストです。
この第3章では、年金受給時期を決めるための「3つの軸」を整理しました。
次章では、よくある疑問に答える Q&A形式 で、実際に迷いやすいケースをさらに具体的に解説していきます。
年金の繰上げ・繰下げを検討する際、多くの方が同じような疑問を抱きます。
ここでは、FP相談の現場で特に多い質問をピックアップし、わかりやすく整理しました。
Q1. 繰下げ受給は本当にお得なの?
💬FPコメント:
私の顧客で、70歳繰下げを選んだ方の多くは「退職金+運用益」で生活費をカバーしていました。
「我慢」ではなく「戦略的な延期」と捉えるのが成功のポイントです。
Q2. 繰上げ・繰下げは一度決めたら変更できない?
これは、“柔軟に繰下げを途中でやめられる”安全弁のような仕組みです。
したがって、65歳以降に働く・健康状態が変化するなど、状況に応じて判断を変えたい方には有効な方法です。
🔹ワンポイント:
・繰上げ開始後は取り消し不可。
・繰下げは途中で請求できる(65〜70歳の間で自由に決定可)。
Q3. 夫婦の年金は同じタイミングで受け取るべき?
💬FPコメント:
ご夫婦の「平均寿命差」「遺族年金」「生活費分担」を考慮して、夫婦単位で受給タイミングを設計すると、安心感が格段に増します。
特に、**夫婦で年金の種類や金額が大きく異なる場合(例:夫は厚生年金、妻は国民年金のみ)**は、タイミングをずらすことで家計のバランスが取りやすくなります。
Q4. 働きながら年金はもらえるの?
💬FPコメント:
「働きながら年金をもらう」ことは可能です。
たとえ在職老齢年金で一部が減額されても、給与収入がある分、世帯全体の手取りはむしろ増えるケースが多いのです。
つまり、“損をする”わけではありません。
ただし、フルタイムで働き続けると税・社会保険料の負担も増えるため、働く時間を少し調整してバランスを取るのが現実的です。
▶関連リンク:年金との兼ね合いを考えた働き方選択(在職老齢年金制度など)
Q5. 繰下げしても途中で亡くなったら損になる?
💬FPコメント:
「損得」ではなく、「後半の生活を支える仕組みをどう作るか」が大事です。
年金は“保険”の一部であり、「長生きのリスク」に備える制度でもあります。
Q6. 年金の受給タイミングを決める前に、何を準備すべき?
| 準備項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① ねんきん定期便 | 現在の年金見込額を把握 | 繰上げ・繰下げ時の差額を確認 |
| ② キャッシュフロー表 | 60〜80歳の収入・支出を可視化 | FP相談で作成可能 |
| ③ 健康・家族・ライフプラン | 働く予定・家族構成・生活費を整理 | 「生き方」と「お金」の整合性を確認 |
💬FPコメント:
多くの方が「年金をいつからもらうか」を数字だけで判断しようとしますが、
実際はライフプランを“見える化”することで、迷いがなくなる方がほとんどです。
一度でもキャッシュフロー表を作ってみることを強くおすすめします。
Q7. FPに相談すると何がわかるの?
💬FPコメント:
相談を通じて、「安心できる受給タイミング」と「数字の裏付け」を持てることが最大のメリット。
これは制度の知識よりも大きな価値があります。
この第4章では、よくある疑問とその実務的な答えを整理しました。
次章では、本記事全体をまとめながら、「後悔しない年金戦略」を実現するための行動ステップをお伝えします。
年金の受給開始時期には、「これが正解」という絶対的な答えはありません。
しかし、**“自分にとって納得できる選択”**をするための考え方は明確です。
年金をいつから受け取るかは、単なるお金の問題ではなく、人生の過ごし方の問題です。
健康状態、働き方、家族構成、資産状況――それぞれの違いが「最適な開始時期」を変えます。
FP相談を通じて感じるのは、“損得”ではなく“安心と納得”を基準に選んだ人ほど、老後の満足度が高いということです。
💬FPコメント:
「65歳で始めるのが普通」ではなく、「自分に合ったタイミングを選ぶ」こと。
それが“後悔しない年金戦略”の第一歩です。
| 戦略 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 繰上げ受給(60〜64歳) | 早くもらえる安心。減額は一生続く。 | 体調不安・無収入期間がある人 |
| 標準受給(65歳) | 増減なしの基準型。安定感重視。 | 健康・家計が平均的な人 |
| 繰下げ受給(66〜70歳) | 最大42%増額。長寿ほど有利。 | 健康・資産に余裕がある人 |
💡結論:
どの選択肢も「正解」になり得ます。
重要なのは、“今の生活”と“将来の理想”のバランスを取ることです。
💬FPアドバイス:
一度ライフプランを“数値化”してみると、迷いが消えます。
年金の最適解は、“人生設計の見える化”から見えてくるのです。
年金戦略は、単体ではなく「老後資金設計全体」の中で判断すべきテーマです。
FPに相談することで、次のようなメリットが得られます。
💬FPコメント:
「もっと早く全体を見直しておけば良かった」という声は本当に多いです。
年金戦略は**老後資金の“出口設計”**でもあり、人生後半の安定を左右します。
▶関連リンク:退職金の資産運用・資産管理|失敗しないための分割管理とライフプラン設計
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| Step1 | ねんきん定期便を確認 | 自分の受給見込みを知る |
| Step2 | ライフプラン表を作る | 将来の収支バランスを把握 |
| Step3 | FPに相談・シミュレーション | 客観的に最適な受給時期を確認 |
| Step4 | 配偶者・家族と共有 | 世帯単位での最適化 |
| Step5 | 定期的に見直す | 制度改正や生活変化に対応 |
💬一言アドバイス:
「迷ったら標準、余裕があれば繰下げ、厳しければ繰上げ」――この順序で検討すると、判断が整理しやすくなります。
年金は「制度」ではなく「人生のキャッシュフローを支える仕組み」です。
繰上げ・繰下げ・標準――どの選択肢にも正解はありますが、あなたの生き方に沿った“納得解”こそが最善の答えです。
もし今、「いつから年金をもらうべきか」で迷っているなら、
数字よりもまず、“どう生きたいか”を描くことから始めてみましょう。
その先に、後悔のない年金戦略が必ず見つかります。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム