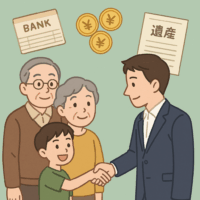
養子縁組は、相続税の節税や相続人間の公平な財産分配を実現する有効な手段のひとつです。
普通養子縁組では法定相続人の数を増やすことができ、相続税の基礎控除や生命保険・退職金の非課税枠を拡大することが可能です。一方で、家族間のトラブルや2割加算の課税リスクなど注意点も少なくありません。
本記事では、養子縁組を利用した相続対策のメリット・デメリット、適用時の注意点やポイントを徹底解説します。
目次
養子縁組とは、法的に親子関係を結ぶ制度で、実子と同様に養子も法定相続人として扱われます。特に相続対策では、養子縁組によって相続人の人数を増やすことで、相続税の基礎控除や非課税枠を拡大できる点が注目されています。
相続税の基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人数」であり、人数が増えるほど課税対象額が少なくなり、税負担を軽減できます。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も「500万円×法定相続人数」となるため、節税効果は大きいといえます。
さらに、相続税は累進課税方式が採用されており、分割によって一人あたりの取得額を減らすことで税率を下げられる場合もあります。
一方、養子縁組は家族間の合意形成や法的手続きが必要であり、節税目的のみで行うとトラブルの原因となることもあるため注意が必要です。相続の公平性や家族の将来を踏まえて、総合的に判断することが重要です。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続対策で一般的に利用されるのは普通養子縁組です。
養子が実父母との親子関係を維持したまま、養父母との親子関係も新たに持つことが特徴です。このため、養子は実父母と養父母の両方の相続権を得ることが可能になります。手続きも比較的簡単で、市役所や役場へ養子縁組届を提出すれば成立します。普通養子縁組には法定相続人に含められる人数制限があり、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までと決められています。
家庭裁判所の許可が必要で、実父母との親子関係が完全に消滅するため、実父母の相続権はなくなります。特別養子縁組は福祉的な目的で使われることが多く、相続対策向きではありません。また、普通養子縁組には法定相続人に含められる人数制限があり、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までと決められています。
この制限を理解したうえで、どの形態が適切かを慎重に選ぶ必要があります。
養子縁組は、相続税の負担を軽減する効果が期待できる代表的な相続対策の一つです。主な理由は4つあります。
これらのメリットを最大限活かすには、事前にシミュレーションを行うことが重要です。
養子縁組は相続税対策として有効な一方で、いくつかのデメリットや注意点があります。
これらを踏まえ、養子縁組はメリットとデメリットを比較したうえで慎重に進める必要があります。
養子縁組は、相続対策や家族の事情に応じて多様なケースで活用されます。
代表的な例としてまず挙げられるのが「孫を養子にするケース」です。これは、世代を飛ばして財産を承継させることで、子→孫と二度課税される相続税を一度にまとめ、節税効果を高める狙いがあります。
次に多いのが「子の配偶者を養子にするケース」です。子の配偶者を養子にすることで、配偶者が直接相続権を持つため、子が先に亡くなった場合でも財産を守りやすくなります。
さらに「再婚相手の連れ子を養子にするケース」もよく見られます。これは、血縁のない連れ子にも相続権を与え、法定相続人として公平な分配を行える点がメリットです。
これらのケースでは、相続税の節税だけでなく、家族間の関係をスムーズにする効果も期待されます。ただし、いずれの場合も親族間の理解を得ずに養子縁組を行うとトラブルになる可能性があるため、事前に十分な話し合いが必要です。
養子縁組を相続対策として活用する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
まず、養子縁組はあくまで「家族関係の形成」という法律上の目的があり、節税目的だけで行うと、税務署から不当な節税と判断され否認される可能性がある点に注意が必要です。
次に、養子縁組をすることで法定相続人が増えると、遺産分割の際に話し合いが複雑になる場合があります。そのため、事前に家族全員の合意を得ることが極めて重要です。
また、普通養子縁組には法定相続人に含める人数制限(実子がいる場合は養子1人まで、いない場合は2人まで)があるため、シミュレーションを行い最適な人数を決める必要があります。
さらに、養子縁組による節税効果を正確に把握するために、財産総額や相続税の試算を専門家と行うことが望ましいでしょう。相続対策で養子縁組を検討する際は、法的リスクと税務面のメリットを総合的に判断することが大切です。
養子縁組は、相続税の節税や家族間の財産承継を円滑に進めるうえで有効な方法の一つです。
普通養子縁組を行えば、相続人の数が増えることで基礎控除額や生命保険・退職金の非課税枠を拡大でき、累進課税の影響を軽減できるため、結果として相続税の総額を抑える効果が期待できます。また、孫や子の配偶者、再婚相手の連れ子を養子にすることで、家族の公平性を保ちながら財産を承継できるというメリットもあります。
一方で、相続人が増えることで一人あたりの相続分が減少し、遺産分割協議でトラブルが起きるリスクがある点や、孫を養子にする場合に相続税が2割加算されるデメリットも見逃せません。さらに、被相続人に兄弟姉妹がいる場合には、養子縁組を行うことで基礎控除が減少し、かえって相続税が増えるケースもあるため注意が必要です。
養子縁組を検討する際は、税務面の試算だけでなく、家族全員の理解と合意を得ることが不可欠です。相続や税務の専門家と相談し、メリットとデメリットを比較したうえで最適な選択をすることが、円満かつ効率的な相続を実現するためのポイントとなります。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム