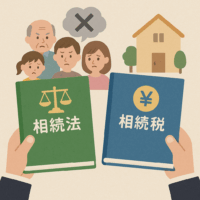
「相続は民法と税法、どちらのルールに従えばいいの?」
実は、ここを正しく理解していないことで、相続トラブルや想定外の税負担が発生するケースは少なくありません。
民法は、誰が何を相続するかといった「権利関係」を定める法律であるのに対し、相続税法は「税金の計算ルール」に関する法律です。
この2つの法律には考え方にズレがあり、放棄・贈与・養子・生命保険・不動産の評価など、さまざまな場面で扱いが異なります。
本記事では、民法と相続税法の代表的な違いを実例とともにわかりやすく解説します。
相続に関わるすべての方にとって、将来のトラブル回避と円満な相続の実現に役立つ内容となっています。
目次
相続人が相続を「放棄」するケースは珍しくありません。多額の借金を抱えていたり、家族の事情で相続を辞退したいという場面もあります。
ただし、民法と相続税法ではこの“放棄”の扱いが異なることをご存じでしょうか?
まず、民法上の相続放棄では、放棄した人は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされます。たとえば、父が亡くなり、相続人が子ども1人だけだった場合、その子が相続放棄をすると、民法では第3順位にあたる父の兄弟が新たに相続人となります。
一方で、相続税法の考え方は異なります。相続税を計算する際は、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数をカウントします。つまり、民法上では相続人から外れていても、税法上は「いるもの」として扱われるのです。
この違いは、相続税の基礎控除額の計算に影響します。基礎控除は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数という式で算出されます。民法上は4人の兄弟が相続人でも、相続税法では放棄した子ども1人だけが法定相続人とされ、「3,600万円」しか控除されません。そのため、想定よりも課税対象額が大きくなる可能性があります。
このように、「相続放棄=すべて関係なくなる」と思っていると、税務上の落とし穴に陥ることも。相続放棄をする際は、民法と相続税法の両面から影響を確認し、専門家に相談するのが安心です。
相続の場面でよく問題になるのが、「生前贈与」の取り扱いです。生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、それを“なかったこと”にはできません。そこで出てくるのが「持ち戻し」という考え方です。
この「贈与財産の持ち戻し」についても、民法と相続税法でルールが異なります。
民法では、生前贈与を受けた人が他の相続人より多くの財産を受け取っていた場合、それを「特別受益」として扱います。
この特別受益は、相続分の計算に反映させるため、原則として時期に関係なく持ち戻しの対象となります。
さらに、相続人の遺留分(最低限保証される取り分)を算定する際には、死亡前10年以内の贈与が対象です。
つまり、「何年も前に親から贈与された土地」でも、相続時には再評価して、相続分を調整する必要があるケースがあります。
相続税法では、被相続人が亡くなる前7年以内に行った贈与について、原則として相続財産に持ち戻して課税します。
ただし、1年目・2年目・3年目の贈与については、相続時精算課税制度を選択しているかどうかによっても加算の仕方が異なります。この「7年ルール」は、税務上の公平性を保つためのものであり、過去の贈与を相続税逃れとみなさないようにするためのものです。
実務でよくある混乱とは?
たとえば、親から生前に住宅取得資金として1,000万円の贈与を受けていた長男がいた場合──
民法ではこの贈与が「特別受益」として他の相続人と公平に分け直す要因となり、
相続税法では、その贈与が7年以内なら相続財産に加算されて課税対象となります。
このように、民法は「相続の取り分」に影響し、相続税法は「課税対象額」に影響するため、両方を理解せずに話を進めると、遺産分割協議と相続税申告で整合性が取れなくなることもあります。
相続対策の一つとして「養子縁組」を活用するケースがあります。
特に、法定相続人の数を増やすことで相続税の基礎控除を引き上げる目的で養子を迎える方も少なくありません。
ただしここで注意すべきなのが、民法と相続税法で「養子の扱い方」が違うという点です。
民法では、養子縁組の数に上限はありません。
実子がいてもいなくても、何人でも養子にすることが可能です。
養子は実子と同じく「子」として扱われ、遺産の相続権も等しく認められます。
したがって、民法上は何人でも相続人として認められるため、養子も実子と同じように遺産分割協議に加わることができます。
一方、相続税法では養子を無制限に法定相続人として認めることはできません。
これは、養子の人数を増やすことで基礎控除額を不当に拡大し、相続税負担を軽減させることを防ぐためです。
相続税法上、法定相続人としてカウントできる養子の人数には以下のような制限があります:
この制限は、「基礎控除額」「生命保険・死亡退職金の非課税枠」「税率の区分」など、相続税のさまざまな計算項目に影響します。
実務で注意したいポイント
たとえば、被相続人に実子1人と養子2人がいる場合──
民法では相続人は3人として扱われ、遺産分割協議では全員が対象になります。
しかし相続税法では、養子1人までしかカウントできないため、法定相続人は2人扱いとなります。
その結果、基礎控除額が小さくなり、想定よりも相続税が増えるケースがあるのです。
相続の場面でよく話題に上るのが、「生命保険の死亡保険金」です。
受取人を指定していた保険金はスムーズに支払われるため、相続対策としても活用されていますが、民法と相続税法での取り扱いが大きく異なる点には注意が必要です。
民法では、受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではなく、受取人個人の固有の財産とみなされます。
そのため、原則として以下のような扱いになります。
特に注意したいのは、「相続財産ではない」とはいえ、一部の財産を受け取って使ってしまうと、放棄が認められない可能性があることです。
葬儀費用の支払いなどで相続財産に手をつけた場合、「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
一方で相続税法では、受取人が相続人である生命保険金は**「みなし相続財産」として相続税の課税対象**になります。
つまり、実際には相続財産でなくても、相続で得た財産と同様に課税されるのです。
たとえば次のような契約形態の場合は、相続税が課されます:
なお、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠が適用されますが、この「法定相続人の数」も放棄の扱いなどで計算が変わるため、正確な判断が必要です。
また、契約者が相続人である場合は、「相続」ではなく「一時所得」として所得税の課税対象になります。
相続財産の中で、特にトラブルや誤解が生まれやすいのが不動産です。
なぜなら、民法と相続税法では「不動産の評価方法」に違いがあり、遺産分割と税金計算で使う数字がズレるからです。
民法では、遺産分割のための不動産の評価額について、明確なルールは定められていません。
そのため、相続人同士が話し合って合意すれば、どの価格を基準にしても問題ありません。
実際には「相続税評価額」や「固定資産税評価額」を参考にすることが多いですが、
相続人間で不動産の分け方や取得者が揉めている場合には、実勢価格(時価)を基準にして主張が対立することもあります。
たとえば、長男が親と同居していた家にそのまま住み続けることになった場合、
他の兄弟が「時価で計算して分けるべき」と主張すると、不公平感や感情的な対立が生じることもあります。
一方、相続税法では不動産の評価について詳細なルールが決められています。
原則として、「財産評価基本通達」に基づいて、以下のように評価されます:
たとえば、路線価は公示価格(実勢価格)の約8割程度で設定されているため、税務上の不動産評価は時価よりも低く出る傾向があります。
この評価差は、税額を抑える意味ではメリットですが、
一方で遺産分割時には「こんな安い金額で計算するの?」と不満が出る要因にもなります。
実務上のポイント
不動産は、相続財産の中でも特にトラブルが発生しやすい資産です。その理由のひとつが、「評価額」に対する認識のズレにあります。
民法では、不動産をどの価格で評価するかに明確なルールはなく、相続人同士の話し合いによって自由に決めることができます。
しかし、相続税法では路線価や固定資産税評価額など、一定の基準で厳密に評価する必要があります。
この「評価の自由」と「評価の厳格さ」の違いが、相続の現場で摩擦を生む原因になるのです。
実勢価格と税法上の評価額のギャップ
実際の不動産取引で用いられる価格、いわゆる「実勢価格(時価)」は、相続税評価額よりも高くなる傾向があります。
たとえば、路線価による土地評価額が2,000万円であっても、
実際にその土地を売却すれば3,000万円になることも珍しくありません。
このとき、ある相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う場合に、
「2,000万円を基準にするのか」「3,000万円を基準にするのか」で意見が分かれることがあります。
よくあるトラブル例
このように、不動産は単に資産価値の問題にとどまらず、家族間の感情や生活に直結する問題にもなるのです。
解決のためのポイント
ここまで見てきたように、相続には「民法」と「相続税法」という2つの異なる視点が存在します。
どちらも“相続”に関わる法律ではありますが、目的や考え方がまったく異なるため、同じ事象でも扱いが違うことが少なくありません。
たとえば、相続放棄をしたつもりでも、税法上は相続人としてカウントされていたり、贈与を受けたつもりが、相続分や課税額に影響していたり、養子の人数が多いことで税法上の控除が適用されなかったりと、「知らなかった」では済まされないギャップが数多く存在します。
特に問題になりやすいのが、不動産の評価です。民法上では相続人同士の合意で価格を自由に決められますが、相続税申告では厳格に決められた評価基準を使わなければならず、そのズレが相続人間のトラブルや不満につながる原因になります。
相続を円満に進めるために大切なこと
相続は、お金の問題であると同時に、家族関係をどう守るかの問題でもあります。
相続人それぞれの事情や立場に配慮し、「損得」だけでなく「心情面」にも目を向けることで、
自然と納得のいく着地点が見えてくるはずです。
おわりに
民法と相続税法の違いを理解しておくことは、相続トラブルを防ぎ、円満な財産承継を実現する第一歩です。
相続に直面したときに慌てないよう、そして将来の家族に負担を残さないよう、
今からできる準備を始めてみませんか?
ご不安なことがあれば、どうぞ専門家へお気軽にご相談ください。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム