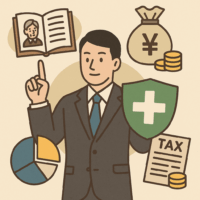
「孫が生まれたので、お祝いに学資保険に入ってあげたいんです」
「将来の大学費用の足しになるように、今のうちに300万円くらい贈与しようかと…」
50代・60代のご相談者様から、このような温かいご相談をいただく機会が増えました。
かわいいお孫さんのために何かしてあげたい。そのお気持ち、とてもよく分かります。
しかし、FPとして、時には心を鬼にしてこうお伝えすることがあります。
「今の時代、学資保険だけはやめておいた方がいいかもしれません」
なぜなら、昭和・平成の常識だった「元本保証の学資保険」は、令和のインフレ時代においては、**「安全に見えて、実は孫の資産を減らしてしまう(インフレ負けする)選択」**になりかねないからです。
この記事では、前半で**「孫への賢い教育資金の渡し方(攻めの対策)」を、後半では「不動産オーナーが絶対にやるべき保険活用(守りの対策)」**を解説します。
次世代に資産を円満に残すための「完全ガイド」としてお役立てください。
目次
先日、62歳のA様(男性)が事務所にいらっしゃいました。
初孫が生まれた喜びでいっぱいのA様。「私がスポンサーになって、孫が18歳になった時に満期になる学資保険に入りたい。元本割れしない安全な商品で」というご希望でした。
一見、堅実で素晴らしいおじいちゃん孝行に見えます。
しかし、私はシミュレーション画面を見せながら、こうアドバイスしました。
「Aさん、この商品なら確かに元本は割れません。しかし、18年後の物価が今より20%上がっていたらどうでしょう? お孫さんが受け取る満期金の価値は、実質的に目減りしてしまいます。今のインフレ時代に、18年間も『利息がつかない場所』にお金を固定するのはリスクが高すぎます」
A様はハッとした表情をされ、最終的に**「変額保険(運用型)」と「贈与」を組み合わせたプラン**を選択されました。
「元本保証=安全」というのは、**「物価が変わらないデフレ時代」**だけの常識です。
今の日本は、30年ぶりに本格的なインフレ(物価上昇)局面に入りました。
仮に、今後も**「年2%」のペースで物価が上がり続けた**とします。
今、必死に貯めた「300万円」は、18年後(大学入学時)にはどうなっているでしょうか?
額面300万円 → 実質価値 約210万円(▲30%ダウン)
※物価上昇により、買えるモノが激減します。
額面315万円 → 実質価値 約220万円(やはりマイナス)
※わずかな利息ではインフレに追いつけません。
額面約600万円 → 実質価値 約420万円(プラス成長!)
※インフレ率を超えて資産が増えるため、購買力を維持・向上できます。
これが**「インフレという見えない泥棒」の正体です。
安全だと思って選んだ元本保証が、結果的に「孫へのプレゼントを小さくしてしまう」**のです。
では、どうすればいいのか?
私がA様にご提案したのは、**「資金は祖父母が出し、運用は親(子世代)が行う」**というハイブリッドな方法です。
ここがポイントです。祖父母が自分で保険に入ってはいけません。年齢が高いため保険料の多くがコスト(危険保険料)に消え、肝心のお金が増えないからです。
贈与したお金の一部を、親のNISA口座で運用してもらうのも有効です。運用益が非課税になり、複利効果で雪だるま式に教育資金が増えます。
このスキームを実行する際、絶対に守らなければならないルールがあります。
それは、「名義預金(実質的には祖父母の財産)」とみなされないことです。
ただ単に親の口座にお金を振り込むだけでは、将来相続が発生した際に「これはお爺ちゃんのお金ですよね?」と税務署に指摘され、相続財産に持ち戻される(課税される)リスクがあります。
これを防ぐために、以下の3点を徹底してください。
面倒でも、お金を移すたびに「贈与契約書」を作成し、双方(祖父母と親)が署名・押印して保管します。「あげた・もらった」の証拠を残すためです。
手渡しはNGです。通帳に記録が残るよう、必ず銀行振込で行ってください。
「孫のための通帳だから」と祖父母が保管していると、名義預金とみなされます。必ず受贈者(親)自身が管理し、自由使える状態にしておく必要があります。
さて、ここまでは「孫への攻めの贈与」の話でした。
しかし、不動産オーナー様からのご相談を受けていると、**「孫の学費の心配より、ご自宅の相続問題の方が深刻ですよ」**というケースが多々あります。
FPとしてもう一つ確認させてください。A様ご自身の「相続対策(守り)」は万全でしょうか?
ここで、生命保険が持つ本来の強力な機能(元記事のテーマ)を2つ、思い出してください。
相続財産が「実家(3,000万円)」と「預金(500万円)」しかない場合、兄弟2人でどう分けますか?
実家を物理的に半分に割ることはできないため、多くのケースで**「実家を売却して現金を分ける」**ことになります。
しかし、「長男家族が同居していて売りたくない」場合どうするか?
ここで登場するのが**「生命保険を使った代償分割」**です。
活用事例
「家はあるけど金がない」というご家庭こそ、生命保険で「調整用の現金」を作っておくべきなのです。
もし、あなたが銀行に2,000万円の預金を持っているとします。そのまま亡くなれば、2,000万円全額に相続税がかかる可能性があります。
しかし、これを生命保険に移し替えるだけで、以下の非課税枠が使えます。
生命保険の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、妻と子2人(計3人)がいる場合、1,500万円まで非課税になります。
ただ「預金の場所を保険会社に変える」だけで、相続税評価額をゼロにできるのです。
「孫への贈与」はコツコツ行う対策ですが、この非課税枠活用は**「契約した瞬間に完了する最強の節税」**です。まだ枠が余っているなら、使わない手はありません。
「孫への教育資金(攻め)」と「ご自身の相続対策(守り)」。
この2つをバランスよく行うことが、資産管理の正解です。
「現金」や「元本保証」に固執することが、必ずしも家族を守ることにはなりません。
時代が変われば、愛の届け方も変わります。
「孫への贈与プラン」と「ご自身の相続シミュレーション」、一度セットで見直してみませんか?
この記事を読んだあなたへ
お孫さんへの資金援助と一緒に、
ご自宅の「相続トラブル対策」も済ませておきませんか?
「うちは大丈夫」と思っている方ほど危険な落とし穴があります。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム