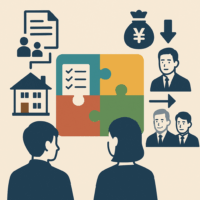
相続対策とは、遺産分割や納税資金、節税、不動産整理、事業承継など幅広い分野にわたる総合的な取り組みです。1つの対策だけに偏ると、他の相続対策へ悪影響を及ぼし、家族間トラブルや「争族」を招く恐れがあります。
本記事では、相続対策の全体像と優先順位、遺産分割対策・節税対策・不動産対策・事業承継対策のポイントや注意点を分かりやすく解説します。現状を整理し、円満な相続を実現するための基本ステップを確認しましょう。
相続対策とは、遺産分割対策・納税資金対策・相続税の節税対策・相続手続き対策・不動産対策・事業承継対策など、複数の分野を総合的に組み合わせて行う必要があります。
特定の対策だけに注力すると、他の対策に悪影響を与えるケースも少なくありません。たとえば、節税を目的に不動産を購入した結果、分割が難しくなり、相続人同士でトラブルが生じることもあります。
そのため、相続対策を実行する際は、まず全体像を把握し、各対策のメリットとデメリットを整理したうえで優先順位を決定することが重要です。
一般的には、「誰が、どの財産を、どのように承継するか」を明確にする遺産分割対策が最優先。その後、納税資金の確保や相続税の軽減策を検討する流れが望まれます。
家族全員のライフプランを踏まえ、円満で効率的な相続計画を立てることが、失敗しない相続の第一歩です。
遺産分割対策は、相続人同士の争いを防ぐ「争族対策」とも呼ばれ、相続対策の中でも特に重要な分野です。
誰がどの財産を、どの割合で、どのように承継するのかを事前に明確にすることで、家族間のトラブルを未然に防げます。特に遺言書の有無は分割方法に大きな影響を与えます。遺言書があれば、基本的にその内容に沿って遺産が分けられますが、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定されます。
しかし、生前贈与の有無や介護負担の偏りなど、相続人間の状況や感情が複雑に絡むことで協議が難航することも少なくありません。近年は権利意識の高まりもあり、争いを防ぐために公正証書遺言の作成や専門家による分割プランの策定が重要視されています。円満な相続を実現するには、被相続人の意思を明確に示し、相続人が納得できる仕組みを生前に整えることが鍵となります。
相続税は高額になることが多く、特に相続財産の大部分が不動産の場合、現金での納税資金を準備するのが難しくなることがあります。流動性が低い不動産ばかりを相続すると、納税資金を確保できずに「相続破産」に陥るケースもあります。
これを防ぐためには、相続税額の試算を早めに行い、必要な納税資金を確保するための計画を立てることが重要です。
納税資金の対策としては、生命保険を活用して現金を準備する方法や、不要な不動産・資産を生前に整理して売却する手段があります。
また、相続税の分割納付(延納)や不動産を担保にした物納といった制度もありますが、手続きは複雑で事前準備が不可欠です。
納税資金対策は、遺産分割対策と並行して考えるべき課題であり、どの資産を承継し、どのように納税するかを家族と共に話し合い、具体的な資金計画を作ることが、円滑な相続への第一歩となります。
相続税は、遺産総額が大きいほど税額も高くなり、将来発生する“借金”のような負担ともいえます。そのため、相続が始まる前から計画的に節税対策を行うことが重要です。
代表的な方法には、生前贈与の活用や、土地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例の適用、養子縁組による基礎控除の拡大などがあります。これらを組み合わせることで、相続税を大幅に抑えることが可能です。
しかし、節税だけを優先すると、かえって遺産分割が難しくなるリスクがあります。たとえば、節税目的でアパートを建てた結果、相続人間で分割が困難になり、争いの火種になることもあります。
そのため、まずは遺産分割対策を整えたうえで、納税資金の確保、最後に節税策を検討するという順番が大切です。
家族の将来の生活を見据え、無理のない節税計画を立てることが円満な相続の鍵となります。
相続が発生すると、名義変更や相続税申告、預貯金の解約など、さまざまな相続手続きが必要となります。これらの手続きには期限があり、煩雑かつ専門知識が求められるため、準備不足だと家族に大きな負担をかけることになります。特に、相続人が遠方に住んでいたり、高齢で対応が難しい場合には、手続きの遅延や不備が生じやすくなります。
こうした問題を回避するには、生前に財産の全体像を把握し、エンディングノートや財産目録を作成しておくことが効果的です。使っていない口座や不要な資産は整理・解約し、借入金の有無も明確にしておくとスムーズです。また、相続手続きが複雑になりそうな場合には、遺言書に専門家を遺言執行者として指定することで、手続きをスピーディかつ確実に進められます。
事前の整理と準備が、相続時の混乱を防ぐ大切なポイントです。
不動産は、相続財産の中で大きな割合を占めることが多い資産です。
しかし、現金のように分割しにくく、相続人間での取り分を調整するのが難しい点が特徴です。また、市場価格と相続税評価額が異なり、換金にも時間がかかるため、納税資金の準備に支障をきたすこともあります。さらに、利用していない土地や建物がある場合、管理費や固定資産税がかかり、いわゆる「負動産」となって相続人に負担を与える可能性もあります。
不動産対策としては、アパート経営や貸地などによる活用で相続税評価を下げる方法や、不要な不動産を生前に売却・整理することが有効です。また、相続開始前に不動産の評価額を把握し、分割方法を明確に決めておくことで、遺産分割のトラブルを回避しやすくなります。
相続人全員が納得できる形で承継できるよう、早めの不動産整理と対策を進めることが重要です
中小企業や同族会社にとって、事業承継は相続対策の中でも特に重要な課題です。経営者が突然亡くなった場合、後継者が決まっていないと会社経営が滞り、従業員や取引先にも大きな影響を与えかねません。また、株式の評価額が高いと相続税の負担が重くなり、事業資金を圧迫することもあります。
事業承継対策としては、後継者を早期に選定・育成すること、株式の分散防止、株価の引き下げ対策、事業承継税制の活用がポイントです。特に株価対策は、財務内容や利益計画の見直し、持株会社の設立など多角的に検討する必要があります。
さらに、親族間の争いを防ぐために、株式の承継ルールや経営方針を明確にしておくことが重要です。事業承継は一朝一夕にできるものではなく、10年単位での計画が必要になることもあります。
経営の安定と会社の存続を守るため、早めの対策と専門家の活用が不可欠です。
相続対策は、遺産分割、納税資金、節税、不動産整理、事業承継など多くの分野が複雑に関わり合うため、全体像を把握して計画的に進めることが不可欠です。どれか1つの対策だけに偏ると、他の分野に悪影響を与え、結果として家族間のトラブルや相続税負担の増加につながることがあります。
特に大切なのは、「遺産分割対策 → 納税資金対策 → 節税対策」という優先順位を意識し、まずは円満に財産を分ける仕組みを整えることです。そのうえで納税資金を確保し、無理のない節税策を実行することで、家族全員が納得できる相続が実現します。
相続対策の本来の目的は、財産を減らさないことだけではなく、家族の生活を守り、安心できる未来をつくることです。現状の整理と早めの準備、そして専門家との相談を通じて、家族にとって最良の相続計画を構築しましょう。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム