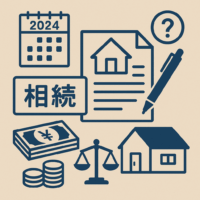
2024年4月1日から、「相続登記の義務化」 がスタートしました。
これまでは、相続で不動産を取得しても登記(名義変更)をしないまま放置しても罰則はなく、その結果、所有者不明土地 が全国で増加し、大きな社会問題になっていました。
改正不動産登記法により、これからは 相続開始または所有権取得を知った日から3年以内 に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料 の対象となり、過料を払っても登記義務は消えません。
では、この相続登記は 自分でできるのか、それとも 司法書士に依頼すべきなのか。
必要書類や費用、手続きの流れを知れば、自分でできるケースも多くありますが、権利関係が複雑な場合や相続人が多い場合は、専門家に依頼する方が安心です。
さらに、相続登記が終わった後の不動産はどうすべきかも重要なポイントです。放置すれば「負動産」になる可能性もありますが、売却・賃貸・活用などライフプランに合わせた選択肢があります。
本記事では、相続登記の義務化のポイント・自分でできるかの判断基準・費用相場・登記後の不動産活用方法 を、わかりやすく解説します。
目次
相続登記 とは、相続で取得した不動産を 相続人の名義に変更する登記手続き のことです。
たとえば、親が所有していた土地や建物を相続した場合、その名義を自分の名前に変更するのが「相続登記」です。
これまで相続登記は義務ではなく、放置しても罰則はありませんでした。
しかし、その結果、登記簿上の所有者が亡くなったまま何十年も放置され、誰が本当の所有者かわからない土地(所有者不明土地) が全国で急増しました。
国土交通省の調査によると、この所有者不明土地は 九州本島の面積を上回る規模 にまで広がり、公共事業や民間の土地活用を妨げる深刻な社会問題になっています。
こうした問題を解消するため、不動産登記法の改正 により 2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。
正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料 が科されます。
注意したいのは、過料を支払ったとしても 相続登記の義務は残る という点です。
つまり、「罰金を払えばやらなくていい」というものではありません。
相続登記を「今は使わないから…」と後回しにしてしまう方は少なくありません。
しかし、放置すれば放置するほどリスクは大きくなり、将来的には登記がほぼ不可能になるケース もあります。
相続登記を長期間行わずに放置すると、相続人が次々と亡くなり、その子や孫に権利が移っていきます。
結果として、相続人の人数がネズミ算式に増加。
こうなると、遺産分割協議すら成立せず、事実上登記ができなくなります。
不動産の名義を変えるために膨大な時間と労力が必要になり、最悪の場合は裁判を経なければならないこともあります。
不動産を売却するには、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致していること が必須です。
相続登記をしていない場合、登記簿上は亡くなった方のままです。
たとえ「今は売らない」つもりでも、将来急に売却や担保設定が必要になった時に、相続人が協力してくれなければ取引そのものが不可能になります。
相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、その人の債権者は 法定相続分による相続登記を代わりに申請 し、持ち分を差し押さえることができます。差し押さえられた持ち分は競売や売却にかけられ、第三者が共有者として登場することになります。この場合、残りの相続人だけでは不動産の売却や活用を自由に決められず、第三者の同意が必要になります。結果として、不動産の自由な利用が大きく制限されます。
2024年4月からの相続登記義務化に合わせ、「すぐに相続登記ができない場合の救済策」 として新設された制度が 相続人申告登記 です。
これは、相続人が法務局に対して、
相続登記は、遺産分割がまとまらない場合や、相続人の中に音信不通の人がいる場合など、すぐに手続きを進められないケースがあります。こうした状況でも、相続登記の義務化による過料(罰則)を避けるための救済制度として、この申告登記が作られました。
結論から言えば、相続登記は自分で行うことが可能です。
法務局の窓口や公式サイトには申請書のひな型や記入例が用意されており、必要書類を揃えて正しく申請できれば、専門家に依頼しなくても手続きは完了します。ただし、相続人が多い場合や権利関係が複雑な場合 は、書類作成や調整に時間と労力がかかるため、司法書士に依頼したほうがスムーズです。
相続登記を行うには、以下の書類が必要です。
※書類は市区町村役場や法務局で取得できます。
相続登記はおおまかに以下の流れで進めます。
メリット
デメリット
相続登記は自分でもできますが、相続人が多い・権利関係が複雑・遠方に不動産がある といった場合には、書類の収集や申請手続きが非常に手間となります。こうしたケースでは、不動産登記の専門家である司法書士 に依頼することで、短期間で正確に登記を完了させることが可能です。
司法書士に依頼する場合、費用は以下のようになります。
| 費用項目 | 相場(目安) |
| 司法書士報酬 | 5万~15万円円程度 |
| 登録免許税(法務局へ納付) | 固定資産税評価額×0.4% |
| 書類取得費用 | 数千円〜1万円程度 |
※不動産の数や所在地、相続人の人数などによって費用は変動します。
相続登記が完了すると、その不動産は正式に自分(または相続人)の所有物になります。しかし、相続登記をしただけで問題が解決するわけではありません。むしろ、その後の管理や活用を考えなければ、「負動産」化するリスクがあります。
相続登記が終わった不動産は、次のような方法で活用できます。
2024年4月からスタートした相続登記の義務化は、すべての不動産相続人に関わる重要なルールです。
「まだ使わないから後で…」 という先延ばしは、将来大きなトラブルを招きます。
相続登記は、やろうと思えば比較的短期間で完了しますが、「やらないまま時間が経つ」 ことで一気に難易度が上がります。
特に複数の相続が重なった場合や相続人が行方不明の場合は、登記が事実上不可能になることもあります。
そのため、相続発生後はできるだけ早く行動を起こすことが、最も重要なポイントです。
相続登記は義務化により「やらなければならない手続き」になりましたが、同時に将来の資産管理と家族の安心を守る第一歩でもあります。早めに・確実に・計画的に進めることで、不動産を「負の遺産」ではなく「価値ある資産」として次世代へ引き継ぐことができます。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム