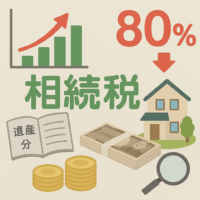
「うちは実家を継ぐ息子と同居しているから、相続税は安くなるはず」
「親が老人ホームに入ったけれど、実家はそのままにしているから大丈夫」
もしそう安心してしまっているなら、少し危険かもしれません。
土地の評価額を最大80%も下げられる最強の節税カード「小規模宅地等の特例」。
確かに効果は絶大ですが、実は**「使えるつもりでいたのに、要件を満たせず使えなかった」**という悲劇が後を絶たない制度でもあります。
「住民票はあるけれど生活実態がない(とみなされた)」
「老人ホームに入所した後、実家を誰かに貸してしまった」
たったこれだけのことで、数千万円単位の節税効果が吹き飛び、莫大な相続税が降りかかってくるのです。
この記事では、教科書的な要件解説ではなく、FPの視点で**「多くの人が勘違いしやすい落とし穴」と、確実に特例を使うための「生活実態の整え方」**について解説します。
目次
「たかが特例一つでしょ?」と侮ってはいけません。この制度の威力は凄まじいものがあります。
例えば、都内に路線価で「5,000万円(330㎡以下)」の土地を持っている場合を見てみましょう。
特例を使えない場合: 評価額は5,000万円のまま。
特例を使えた場合: 評価額は1,000万円(80%減)になります。
その差はなんと4,000万円です。
もし相続税率が30%のご家庭なら、税金が「1,200万円」も安くなる計算です。
逆に言えば、特例適用に失敗すると、1,200万円を現金で即納しなければなりません。
この特例が使えるかどうかは、単なる節税レベルの話ではなく、**「代々受け継いだ実家を売らずに守れるかどうか」**の分かれ道なのです。
国税庁にとって、この特例は「生活の基盤(家や店)を守るための救済措置」です。
「相続税を払うために住む家を売らなきゃいけない」という事態を防ぐための優しさであって、「単なる節税テクニック」として使われることを極端に嫌います。
そのため、税務署は形式(住民票)だけでなく、**「実態(本当にそこで暮らしていたか)」**を徹底的に見ます。
ここを甘く見ていると、税務調査で否認されるリスクが高まります。
私が相談を受ける中で、特に多い「危ない勘違い」を3つご紹介します。
「別居している長男の住民票を、とりあえず実家に移しておこう」
これは昔からある手法ですが、現在は通用しません。
税務署は、公共料金の使用量(水道・電気・ガス)、郵便物の転送状況、勤務先への通勤経路などを調べれば、そこに生活実態がないことなどすぐに見抜きます。
「同居」として認められるには、**「生活の財布(生計)を共にしているか」や「日常的に寝起きしているか」**という事実の積み重ねが必要です。
親御さんが老人ホームに入居した場合でも、一定の要件(要介護認定など)を満たせば、実家は「住んでいた」とみなされて特例が使えます。
しかし、ここでよくある失敗が、「空いた実家がもったいないから」と、親族や第三者に貸してしまうことです。
賃貸に出した時点で、その家は「親の住まい」ではなく「貸付用」となり、80%減額(特定居住用)の対象から外れてしまいます(※貸付事業用として50%減額になる可能性はありますが、効果は激減します)。
「良かれと思って」やったことが、相続税を跳ね上げる原因になるのです。
二世帯住宅も特例の対象ですが、**「構造」と「登記」に注意が必要です。
建物内部で行き来できない完全分離型でも特例は使えますが、もし親子で「区分所有登記(1階は親、2階は子)」**をしてしまっていると、特例が適用できない(あるいは土地の一部しか適用できない)ケースがあります。
二世帯住宅を建てる際は、建築会社だけでなく、必ず税理士やFPに「相続時の評価」を確認してください。
税務調査官は、家の中の「生活の匂い」を見ています。
「同居」を主張する場合、以下の項目で、説明できないものはありませんか?
[ ] 親と子の生活スペース(キッチン・風呂)は共有か?別々なら区分登記していないか?
[ ] 親の郵便物は実家に届いているか?(施設に転送設定していないか)
[ ] 公共料金の支払いはどうなっているか?(極端に使用量が少なくないか)
[ ] 週末だけ帰省する「週末同居」になっていないか?
特に「平日は会社の近くに住んで、週末だけ実家に帰っている」というケースは、同居とは認められません。あくまで「生活の本拠地」がどこにあるかが問われます。
将来、税務署に「これは間違いなく同居でした」「生活の拠点でした」と認めてもらうためには、生前の準備がすべてです。
特に「家なき子特例(同居していない親族が相続する場合)」は、持ち家の定義(親族の所有する家に住んでいないか等)が非常に複雑です。自己判断せず、必ず専門家のチェックを受けてください。
Q.将来、家を建て替えても特例は使えますか?
A.はい、要件を満たせば使えます。ただし、二世帯住宅に建て替える場合は「登記の方法(区分所有にしない)」に注意が必要です。必ず建築前にご相談ください。
Q.入院が長引いて、実家に誰もいない期間があっても大丈夫?
A.入院であれば、生活の拠点は実家にあるとみなされるため、基本的に大丈夫です。ただし、入院中に「もう帰れないから」と賃貸に出してしまうと対象外になってしまいますのでご注意ください。
Q. 相続税を払うために、相続してすぐに実家を売却してもいいですか?
A. いいえ、注意が必要です。 特例を使うためには、原則として**「相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)」まで、その土地を持ち続け、住み続ける必要**があります。期限前に売ってしまうと特例が使えなくなるため、売却のタイミングは必ず税理士と相談して決めてください。
小規模宅地の特例は、適用できれば「相続税ゼロ」もあり得る強力な武器です。
しかし、**「特例を使うために、無理やり同居する」「特例のために、不便な二世帯住宅を建てる」**というのは本末転倒です。
大切なのは、ご家族が自然な形で暮らし、その結果として特例が使えるように準備すること。
「うちは今の状況で使えるの?」
「将来、施設に入るときはどうすればいい?」
そんな不安がある方は、申告期限ギリギリになって慌てる前に、一度FPにご相談ください。
小規模宅地の特例は、要件が非常に厳しく、ちょっとした勘違いで数百万円もの節税効果を逃してしまう方が後を絶ちません。
失敗しないためには、元気なうちからの「正しい準備」が不可欠です。
まずは、相続で損をしないための基礎知識を、無料のガイドブックで確認しておきませんか?
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム