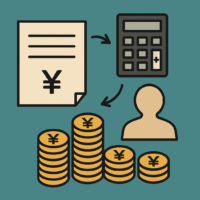
相続の場面でしばしば問題となるのが「遺留分」です。
遺留分とは、配偶者や子、直系尊属などの法定相続人に法律で保障された最低限の取り分のことを指します。たとえ遺言で「全財産を特定の人に贈与する」と定めても、他の相続人には遺留分の請求権があります。
本記事では、遺留分の基礎知識、権利者の範囲、割合、計算方法、そして侵害された場合の請求手続きまでを分かりやすく解説。円満な相続のために遺留分を考慮した遺言作成のポイントも紹介します。
遺留分とは、法定相続人に法律で保障された最低限の相続分を指します。通常、自分の財産は生前・死後を問わず自由に処分できますが、遺言で「全財産を特定の人に贈与する」とした場合でも、一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)には最低限の取り分である遺留分が確保されています。
遺留分は、相続人の生活基盤を守るために設けられた制度であり、兄弟姉妹には認められていません。例えば、被相続人が赤の他人に全財産を遺贈する旨の遺言を残しても、配偶者や子は遺留分侵害請求を行い、法定割合に応じた金銭を請求できます。
円満な相続を実現するためには、遺言書を作成する際に遺留分を意識し、相続人間で不公平感が生まれないよう配慮することが重要です。
遺留分は、すべての相続人にあるわけではなく、兄弟姉妹を除く法定相続人にのみ認められます。
具体的には、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母や祖父母など)が対象です。
例えば、子がいない場合は両親などの直系尊属が相続人となり、その際に遺留分が発生します。また、遺留分の権利は相続により引き継がれるため、二次相続でも遺留分が認められることがあります。
遺留分の割合は、法定相続分に一定割合を掛けて計算します。
例として、配偶者と両親が相続人の場合を見てみましょう。
配偶者の法定相続分は2/3なので、遺留分は 2/3 × 1/2 = 2/6
両親(直系尊属)の法定相続分は1/3なので、遺留分は 1/3 × 1/2 = 1/6
このように、遺言を作る際には遺留分を正しく計算し、相続人間で不公平感が生じないよう配慮することが大切です。
遺留分侵害請求とは、遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害された場合に、相続人がその不足分を取り戻すために行う請求です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月の民法改正により、金銭での支払いを基本とする「遺留分侵害請求」に変更されました。
この制度では、不動産など分割が難しい資産を共有にせず、金銭で補填することで、被相続人の意思(不動産を特定の相続人に残したいなど)を尊重しつつ、他の相続人の権利を守ります。
遺留分侵害請求は、「相続開始と侵害の事実を知った日から1年以内」または「相続開始から10年以内」に行わなければ権利が消滅します。請求はまず当事者同士での話し合いから始めますが、解決しない場合は調停や訴訟に移行します。確実に証拠を残すため、内容証明郵便で請求の意思を伝えることが推奨されます。
遺留分を算出するには、まず相続財産の総額を正確に把握することが重要です。
総額には、遺言や相続で実際に取得した財産だけでなく、相続開始前に行われた一定の贈与も含まれます。具体的には、相続開始1年以内の第三者への贈与や、相続開始前10年以内の特別受益(相続人が生前に特別に受けた贈与や遺贈)が加算されます。これらを合算した総財産額から、被相続人の債務(借金)を差し引いた金額が基礎となります。
計算式は以下の通りです:
{(相続財産 + 1年以内の贈与 + 10年以内の特別受益)- 債務} × 遺留分割合
この計算で求めた遺留分額と、実際に相続で取得した財産額の差額が、遺留分侵害請求できる金額となります。贈与や特別受益の内容は後々トラブルになりやすいため、事前に専門家と相談して算定基準を明確にしておくことが望まれます。
遺留分を無視した遺言や生前贈与は、相続人間の不満や争いを引き起こす原因となります。
円満な相続を実現するためには、遺言作成時に遺留分を考慮することが不可欠です。特定の相続人に偏った財産分配を行う場合は、遺留分を侵害しないよう調整する、もしくは他の相続人に代償金を用意するなどの対策を検討しましょう。
さらに、遺言書には「付言事項」を記載することが有効です。付言事項とは、なぜその相続分配にしたのか、家族への感謝の気持ちや思いを記す文章のことです。これを残すことで、相続人の理解が得られやすくなり、遺留分請求が発生しても話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
遺留分を踏まえたうえでの遺言作成は、家族間の信頼関係を守るための重要なステップです。
遺留分は、配偶者や子、直系尊属など特定の法定相続人に最低限の取り分を保障する制度です。たとえ遺言で自由に財産分配を決めたとしても、遺留分を侵害すると相続トラブルにつながる可能性があります。特に、偏った贈与や特定の相続人への優遇は、後々「遺留分侵害請求」を引き起こす原因となりかねません。
相続を円満に進めるためには、遺言書作成時に遺留分を考慮した財産分配を行うことが重要です。また、遺言書の付言事項で相続に込めた想いや理由を明確にすることで、家族間の理解と納得を得やすくなります。
遺留分の計算や調整は複雑になることも多いため、弁護士や相続アドバイザーなどの専門家に相談し、適切な遺言・贈与計画を立てることが円満な相続への近道といえるでしょう。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム