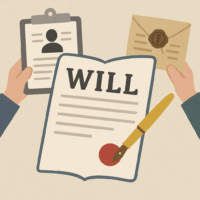
遺言は、自分の想いを家族や大切な人に正しく伝え、相続トラブルを防ぐための重要な手段です。
この記事では、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違いやメリット・デメリット、2020年から始まった自筆証書遺言保管制度、無効を防ぐための書き方、遺言執行者の役割、付言事項の書き方まで分かりやすく解説します。
目次
遺言とは、自分の死後における財産や身分に関する意思を明確に示し、法的効力をもって実現するための重要な手段です。遺言がある場合、民法で定められた法定相続人や法定相続分よりも優先して相続が行われるため、自分の想いを反映した財産分配が可能となります。
特に、子供がいない夫婦で配偶者に多く財産を残したい場合、世話をしてくれた特定の子供に事業や不動産を承継させたい場合、または特定の団体や相続人以外の人物に財産を寄付したい場合には遺言の作成が非常に有効です。
さらに、財産が不動産に偏っている場合、分割方法を明確に記しておくことで、相続人同士の揉め事を防ぐことができます。
遺言は単なる財産分与の手段にとどまらず、相続人に対する感謝や想いを伝える役割も担います。人生の最終メッセージとして、早めに準備することが円満な相続の第一歩といえるでしょう。
遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
公証人が遺言内容を確認し作成する方法で、法的に最も確実性が高く、無効になるリスクがほとんどありません。原本は公証役場で保管され、改ざんや紛失の心配もなく、家庭裁判所での検認も不要です。ただし、公証人への手数料や証人2名の立会いが必要となる点はデメリットといえます。
自分で紙とペンを用いて作成でき、費用がほとんどかからない点が魅力です。しかし、法律の形式に不備があると無効となるリスクがあり、開封時には家庭裁判所での検認が必要です。紛失や改ざんのリスクも課題です。
内容を秘密にしたまま公証人と証人が存在を証明する形式で、作成方法に自由度がある一方、利用者は少なく、実務的には自筆証書遺言と同様のデメリットがあります。
近年、自筆証書遺言はより利用しやすい制度へと改正されました。
以前は遺言の全文を自書しなければなりませんでしたが、現在は財産目録部分のみパソコンで作成したり、預金通帳のコピーや登記事項証明書を添付することが認められています。これにより、財産が多い人でも効率的に作成できるようになりました。
さらに、2020年7月10日からは「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。この制度を利用すると、法務局の遺言書保管所で遺言を預かってもらえます。預ける際には、遺言書保管官による形式面のチェックがあり、無効リスクを減らせる点が大きなメリットです。また、保管された遺言書は原本・画像データとして長期的に保存され、紛失や改ざんの心配がありません。相続開始後の家庭裁判所での検認も不要となり、スムーズな相続手続きが可能になります。これにより、自筆証書遺言はより安全かつ便利な選択肢となりました。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方、法律で定められた要件を満たさなければ無効になるリスクがあります。
まず、遺言の本文・日付・氏名は必ず本人が自書し、署名と押印(認印でも可)を行う必要があります。日付は「令和○年○月○日」と具体的に記載し、曖昧な日付表記は避けましょう。
財産目録をパソコンで作成した場合や、通帳コピーや登記事項証明書を添付する場合は、各ページごとに署名・押印が求められます。
また、本文とは別紙として作成し、財産と相続人が特定できるように明確に記載することが重要です。
記載を訂正する際は、二重線を引き、訂正箇所に押印し、訂正の内容と署名を追加します。この手順を怠ると無効になる可能性があります。
さらに、相続人には「相続させる」、相続人以外の人には「遺贈する」という表現を正しく使い分けましょう。
こうした細かなルールを守ることで、自筆証書遺言の効力を確実にすることができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続手続きを進める人物のことです。例えば、遺産分割や名義変更、相続税申告など、相続全般の実務を円滑に行う役割を担います。遺言書で指定することができ、相続人の同意は不要です。
特に、相続人を廃除する場合や、婚姻外の子を認知する場合には、遺言執行者の指定が必須です。また、相続人に認知症の方がいる、遠方で手続きが困難、あるいは非協力的な相続人がいるなど、トラブル回避のために遺言執行者を選任することは非常に有効です。
遺言執行者は相続人でも構いませんが、感情的な対立を避けるために、弁護士・司法書士・行政書士といった第三者の専門家を選ぶケースが増えています。
専門家を遺言執行者にすることで、法的な知識を活かし、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。遺言の内容を確実に実行するため、信頼できる人や専門家を選ぶことが重要です。
付言事項とは、遺言書の法的効力を持たない部分に、自分の想いや家族への感謝の気持ち、遺言内容の背景などを自由に記すことを指します。たとえば、「介護をしてくれた長女に感謝して自宅を相続させたい」「長男には事業を継いでほしい」といった思いを具体的に書くことで、遺言の意図を明確に伝えることができます。
遺言書の内容が法定相続分と異なる場合、不満を抱く相続人が出ることも少なくありません。こうした場合に付言事項で気持ちや理由を説明することで、納得感が生まれ、相続トラブルを防ぐ効果があります。また、葬儀や納骨の希望、形見分けに関する考えを記載することも可能です。
付言事項は、形式に制約がないため自由に書けますが、文章が長くなりすぎると主文が見えにくくなるため、要点を簡潔にまとめることが望まれます。自分の想いを丁寧に伝えることで、遺言が単なる資産分配の指示ではなく、家族への最後のメッセージとして意味を持つようになります。
遺言は、自分の意思を確実に家族へ伝え、相続トラブルを防ぐための最も有効な手段です。
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のいずれも特徴があり、自分の状況や目的に応じて選ぶことが重要です。特に公正証書遺言は法的効力が高く、自筆証書遺言は費用が抑えられるというメリットがあります。
また、自筆証書遺言保管制度の導入により、自筆証書遺言がこれまで以上に安全かつ便利になりました。遺言の無効を避けるためには、法定要件を正しく守り、財産や相続人を明確に記すことが欠かせません。
さらに、遺言執行者を指定しておくことで、複雑な手続きもスムーズに進みます。
付言事項を活用し、自分の想いや感謝を添えることで、遺言は単なる財産分配の指示書ではなく、家族への最後のメッセージとしての価値を持ちます。
遺言作成は「まだ早い」と思われがちですが、早めの準備こそが安心を生み、家族への最大の思いやりとなります。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム