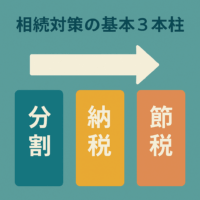
相続対策というと「相続税の節税」に注目しがちですが、実はそれだけでは家族を守ることはできません。相続には、分割対策・納税資金対策・節税対策という3つの柱があり、この順番を誤ると、円満なはずの相続が思わぬトラブルに発展することもあります。
本記事では、FP(CFP®/相続アドバイザー)が最新の制度と実務経験をもとに、3つの柱の意味と優先順位をわかりやすく整理。さらに、関連する詳しい記事へのリンクも掲載し、どこから対策を始めるべきかを具体的に示します。
「家族の絆を守りながら、安心して財産を引き継ぐ」――そのための第一歩として、本記事をハブに相続の全体像をつかみましょう。
目次
相続対策とは、単に「税金を減らす」ための準備ではありません。
本来の目的は、家族が円満に財産を引き継ぎ、生活を安定的に続けられるようにすることです。
そのために必要なのが、次の3つの柱です。
| 柱の名称 | 内容の概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 分割対策 | 誰が・何を・どのように相続するかを明確にする準備 | 家族間のトラブル防止 |
| 納税資金対策 | 相続税を期限内に支払うための資金を確保 | 納税負担の軽減と流動性確保 |
| 節税対策 | 生前贈与や保険・不動産活用などによる税負担の軽減 | 残す財産を最大化 |
多くの方が関心を寄せるのは「節税」ですが、実際には分割対策こそが最優先です。
なぜなら、分け方が決まっていないと、家族の話し合いがまとまらず、相続税を払う以前に“財産が動かせない”状況に陥ることがあるからです。
相続の理想的な進め方は、
①まず分割の方針を固める → ②次に納税資金の準備 → ③最後に節税の工夫を検討
という流れです。
この3本柱の全体像を理解しておくことで、「どこから手をつけるべきか」が明確になります。
🔗 さらに詳しく学ぶならこちら
次章では、3本柱の中で最も重要な「分割対策」について、具体例とともに詳しく解説します。
遺言書・代償分割・家族会議の進め方など、円満な相続を実現するための実践的な手順を見ていきましょう。
相続対策の3本柱の中で、最も重要なのが「分割対策」です。
理由はシンプルで、分け方が決まらなければ何も進まないからです。
たとえ節税に成功しても、財産を誰にどのように渡すかが曖昧なままだと、話し合い(遺産分割協議)が難航し、兄弟姉妹の関係が壊れてしまうことすらあります。
特に不動産が多い家庭では、現金のように均等に分けられないため、トラブルの火種になりやすいのが現実です。
こうした“争続(そうぞく)”を防ぐための第一歩が、遺言書の作成と家族の事前対話です。
💡 遺言書の作成で「想い」を形にする
遺言書は、相続対策の中で最も効果的な「トラブル防止策」です。
被相続人が「誰に・どの財産を・どんな想いで」残すかを明確にしておくことで、相続人同士の不信感や誤解を防げます。
また、法的効力のある公正証書遺言を作成しておくと、後々の手続きもスムーズです。
➡ 遺言の種類と作り方|公正証書・自筆証書・秘密証書の違いと選び方ガイド
不動産を複数の相続人でどう分けるかは、最も悩ましいテーマです。
代表的な方法は以下の3つです。
| 方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 代償分割 | 不動産を1人が相続し、他の相続人に代償金を支払う | 最も現実的・公平性が高い |
| 共有分割 | 相続人全員で持分割合を設定し共有 | 将来の売却時にトラブル化しやすい |
| 換価分割 | 不動産を売却して現金で分ける | 換金性は高いが、思い出資産を手放すケースも |
不動産の評価額や換金性を踏まえて、どの方法が自分たちの家族に合っているかを話し合うことが重要です。
➡ 実家の相続で迷わない!不動産評価・分割・売却の完全ガイド
➡ 不動産の相続税評価額と土地の5つの価格をわかりやすく解説
相続のトラブルは「お金の問題」よりも「気持ちのすれ違い」で起こります。
被相続人が元気なうちに、家族全員で将来の希望や考え方を話し合うことで、相互理解が深まり、遺言の内容も現実的なものになります。
FPとしての立場からも、“遺言+対話”の両輪が最も効果的だと感じます。
➡ 親が元気なうちに始める「相続対策」5ステップ
➡ 相続における「平等は公平ではない」という考え方|家業承継と遺言対策の重要性
分割対策は、家族関係を守るための“設計図”です。
遺言書を通じて意思を明確にし、不動産の分け方を現実的に整理し、家族全員で共有しておく。
この3点を実行するだけで、相続後の混乱の多くを防ぐことができます。
次章では、この分割対策を支えるもう一つの柱「納税資金対策」について、具体的な準備方法を見ていきましょう。
相続税は、原則として相続発生から10か月以内に現金一括で納付しなければなりません。
この期限に間に合わないと延滞税が発生し、最悪の場合は不動産を急いで売却せざるを得なくなるケースもあります。
そのため、節税よりも先に「納税資金の確保」を考えておくことが、実務上きわめて重要です。
| 対策方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 生命保険の活用 | 死亡保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税。保険金が即座に受け取れる。 | 相続税の支払いに最も有効。現金化が早い。 |
| 現金・預金の確保 | 普段から生活費とは別に、納税資金として預金を準備。 | シンプルで確実。運用リスクがない。 |
| 資産の流動化 | 不動産・株式の一部を売却して現金化。 | 納税後の資産バランスも整えやすい。 |
➡ 相続対策における生命保険の有効活用|分割・納税・節税のポイントを徹底解説
納税資金を後回しにすると、以下のような事態が起こりがちです。
こうした失敗を避けるには、「いくら納税が発生しそうか」を早めに試算し、相続税の見積り+資金計画を立てておくことが大切です。
➡ 退職金と相続税・所得税の意外な関係|受け取り方で変わる税負担
➡ 配偶者を守る相続対策|老後資金・節税・居住権まで徹底解説
実際の相談では、節税効果を優先しすぎて現金が足りず、結果的に「資産を減らす行動」に追い込まれるケースが少なくありません。
FPとしては、**「節税より先に納税資金」**を合言葉に、現金の準備を最優先にしています。
生命保険を使えば、節税と納税資金確保を同時に実現できる場合もあります。
納税資金の準備は、家族に負担を残さないための「守りの相続」です。
節税を検討する前に、まず現金で払える体制を整えること。
この順番を守ることで、トラブルを回避し、余裕ある相続が実現します。
次章では、3本柱の3つ目「節税対策」について、効果的な手法と注意点を解説します。
相続税の負担を軽くする「節税対策」は、多くの人が真っ先に関心を持つテーマです。
ただし、節税だけを目的化すると本末転倒。
分割や納税の準備が不十分なまま節税に走ると、結果的に家族のトラブルや資金不足を招くこともあります。
節税は、あくまで「分割と納税の仕組みが整ったうえで行う最終ステップ」と心得ましょう。
| 節税方法 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生命保険の非課税枠活用 | 「500万円×法定相続人の数」まで非課税。納税資金対策も兼ねる。 | 保険金受取人の指定を誤ると効果半減。 |
| 生前贈与 | 暦年課税(年間110万円)や相続時精算課税を活用して早めに資産移転。 | 贈与契約書の作成や贈与実績の証拠が重要。 |
| 不動産活用 | 貸家建築や小規模宅地の特例で土地評価を圧縮。 | 将来の維持費・分割計画を同時に検討。 |
➡ 相続対策になる生前贈与の非課税制度7選と活用ポイント
➡ 不動産でできる相続税対策8選|購入・小規模宅地特例・小口化まで網羅
土地の評価額を下げるために賃貸アパートを建てるなどの不動産活用は、有効な節税策の一つです。
しかし、分割しにくい資産が増えることで、かえって家族間の調整が難しくなることもあります。
節税目的で不動産を動かすときは、分割・納税資金との整合性をFPや税理士と確認しておくことが大切です。
➡ 相続税を最大8割減!小規模宅地の特例の要件・注意点を徹底解説
➡ FPが解説|不動産オーナーの法人化で実現する節税と相続対策
相続の現場で多い失敗は、「節税できたけれど、家族が揉めた」「納税資金が足りなかった」というケースです。
節税とは、**家族全体の相続設計が整った結果として生まれる“副産物”**であり、目的ではありません。
FPとしての立場からも、「節税よりも家族関係の維持と納税準備の優先」を強くおすすめします。
➡ 相続民法と相続税法の違いとは?実例でわかる相続トラブル回避術
節税対策を成功させるコツは、「順番を守ること」。
まず分割、次に納税、最後に節税――この流れを徹底することで、家族関係を守りながら税負担を最小限に抑えられます。
次章では、相続の中でも特に複雑なテーマである「不動産と相続の関係」を整理し、円満に財産を引き継ぐための実践的な視点をお伝えします。
相続財産の中で最もトラブルが多いのが不動産です。
不動産は価値が大きく、分け方によって公平感が揺らぎやすいため、「分割・納税・節税」の3本柱すべてに関わります。
現金のように均等に分けることが難しいからこそ、早い段階で方針を固めることが鍵になります。
| 課題 | 内容 | 解決の方向性 |
|---|---|---|
| 分けにくい | 土地・建物は一部だけ分けにくく、共有すると将来売却で揉めやすい。 | 代償分割や換価分割を検討。 |
| 評価が難しい | 路線価・実勢価・固定資産税評価など「5つの価格」が存在。 | 公的基準での評価と専門家の意見を照らし合わせる。 |
| 流動性が低い | 売却まで時間がかかり、納税資金に間に合わないことも。 | 一部売却や貸出で換金性を高める。 |
➡ 不動産の相続税評価額と土地の5つの価格をわかりやすく解説
➡ 実家の相続で迷わない!不動産評価・分割・売却の完全ガイド
不動産の分け方は、“今の公平”よりも“将来の安心”を基準に決めることが大切です。
例えば、
こうした判断を、感情論ではなくライフプランの延長線上で行うことが、FPとして推奨するアプローチです。
➡ 相続前or相続後?不動産売却で損しないための税金・特例・判断ポイント
不動産は、相続対策の3本柱を結びつける“要”の存在です。
土地の活用や共有形態によって、節税効果・分割のしやすさ・納税資金確保がすべて変わります。
代表的な活用法には以下のようなものがあります。
| 戦略 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃貸化(貸家建築) | 土地評価額を下げて節税。家賃収入で納税資金も確保。 | 将来の管理・空室リスクを考慮。 |
| 法人化 | 不動産所得を法人に移して相続時の課税を分散。 | 設立費用・維持コストに注意。 |
| 家族信託 | 認知症リスクや管理の継続性を確保。 | 契約設計が複雑。専門家と連携必須。 |
➡ FPが解説|不動産オーナーの法人化で実現する節税と相続対策
➡ 家族信託と相続前後の財産管理について
不動産は、財産としての価値だけでなく、家族の思い出・生活基盤・居場所という側面を持ちます。
「資産をどう残すか」と同時に、「どう使い、どう引き継ぐか」を考えることが、後悔しない相続への近道です。
FPとしては、分割・納税・節税を“別々に考えない”ことが最も重要だと感じます。
次章では、長年相続の現場を見てきたベテラン相続アドバイザーの教えを紹介し、家族の絆を守るための考え方を掘り下げます。
相続の現場に長く関わってきて感じるのは、
**「相続の問題は、お金よりも“人間関係”にある」**ということです。
遺産の分け方がきっかけで、兄弟姉妹が疎遠になったり、親の思いが誤解されてしまうケースは少なくありません。
一方で、早い段階から家族が話し合い、互いの想いを共有していた家庭では、どんなに複雑な財産でも不思議とトラブルが起きません。
円満相続の原則は、“仕組み”と“気持ち”の両方を整えることにあります。
| 原則 | 内容 | 実践ポイント |
|---|---|---|
| ① 想いを“見える化”する | 遺言書やメモを通じて意思を明確に伝える | 公正証書遺言+家族への口頭説明 |
| ② 早めに“共有”する | 相続は“亡くなってから”では遅い | 家族会議・FP面談を定期的に実施 |
| ③ 第三者を“交える” | 専門家が入ることで感情論を避けられる | FP・税理士・司法書士と連携 |
ある70代の相続アドバイザーが、次のように話していました。
「相続とは、財産を分けること以上に“縁をどう続けるか”が大切。
財産よりも、“感謝の気持ち”をどう伝えるかが本当の相続なんです。」
この言葉は、数多くの現場を見てきた専門家ならではの実感です。
家族の関係性を守るためには、数字よりも対話、節税よりも信頼を優先する姿勢が欠かせません。
➡ 相続民法と相続税法の違いとは?実例でわかる相続トラブル回避術
➡ 二次相続対策|夫婦のどちらかが亡くなった後に必要な準備
これまで相談を受けてきた中で、円満に相続を終えたご家庭には共通点があります。
それは「家族の想いを尊重する姿勢」が、常に軸にあることです。
こうした“想いの共有”があるご家庭では、財産の多寡に関係なく、結果的に相続が円滑に進み、家族関係も深まる傾向があります。
FPとしても、数字の最適化以上に「心の整理」を支援することを大切にしています。
相続とは、単なるお金の受け渡しではなく、**家族の歴史と想いをつなぐ“人生のバトンリレー”**です。
分割・納税・節税の3本柱を整えることはもちろん大切ですが、最終的に家族の心が離れてしまっては本末転倒。
“誰かが少し譲り、誰かが感謝する”――その循環こそが、幸せな相続のかたちです。
🔗 関連して読みたい記事
ここまでご紹介した「分割・納税・節税」の3本柱を理解したら、
次は実際にご自身の相続準備がどこまで進んでいるかを確認してみましょう。
以下のチェックリストをもとに、今の状況を整理するだけでも、これからの方向性が明確になります。
📋 相続対策セルフチェック
| チェック項目 | 状況 | 関連記事リンク |
|---|---|---|
| ① 家族に伝えたい想いを整理している | □ 済 □ 未 | 親が元気なうちに始める「相続対策」5ステップ |
| ② 遺言書を準備している(または作成予定) | □ 済 □ 未 | 遺言の種類と作り方|公正証書・自筆証書・秘密証書の違いと選び方ガイド |
| ③ 財産の全体像(不動産・預金・保険など)を把握している | □ 済 □ 未 | 相続計画の全体像:子や孫の代まで資産を守る方法 |
| ④ 相続税が発生するかどうかを概算で把握している | □ 済 □ 未 | 相続対策における生命保険の有効活用|分割・納税・節税のポイントを徹底解説 |
| ⑤ 納税資金の準備方法を決めている | □ 済 □ 未 | 退職金と相続税・所得税の意外な関係|受け取り方で変わる税負担 |
| ⑥ 贈与や保険などを活用した節税策を検討している | □ 済 □ 未 | 相続対策になる生前贈与の非課税制度7選と活用ポイント |
| ⑦ 不動産の評価・分割・売却方針を確認している | □ 済 □ 未 | 実家の相続で迷わない!不動産評価・分割・売却の完全ガイド |
| ⑧ 家族で一度は“相続の話し合い”を行っている | □ 済 □ 未 | 相続における「平等は公平ではない」という考え方|家業承継と遺言対策の重要性 |
| ⑨ 二次相続(配偶者死亡後)を見据えた設計をしている | □ 済 □ 未 | 二次相続対策|夫婦のどちらかが亡くなった後に必要な準備 |
| ⑩ 専門家(FP・税理士・司法書士など)に相談したことがある | □ 済 □ 未 | 初回相談のご案内はこちら |
💡 チェックリストの活用法
FPの立場から言えば、“気づいた今が最適なスタートタイミング”。
遺言や贈与といった法的な対策だけでなく、「家族の気持ちを整えること」も、立派な相続対策です。
🧭 次に取るべきステップ
相続対策には「分割対策・納税資金対策・節税対策」という3本柱があります。
どれも欠かせない要素ですが、最も優先すべきは分割対策です。
なぜなら、分け方が決まらなければ、節税も納税も進まず、家族関係に亀裂が入ってしまうことがあるからです。
相続の本質は、“財産を残すこと”ではなく、“想いをつなぐこと”。
遺言書を作り、家族で話し合い、納税資金を準備しながら、できる範囲で節税を組み合わせる。
その一つひとつの積み重ねが、「争わない相続」=円満相続を実現します。
🕊️ 家族の絆を守るために、今できること
相続は“いつかやらなければならないこと”ではなく、**「今から備えられる家族の計画」**です。
まずは現状を整理し、誰が・何を・どのように引き継ぐのかを明確にすることから始めましょう。
FPや税理士、司法書士などの専門家と協力すれば、感情面・税務面・法務面すべてをバランスよく整えることができます。
💬 最後に:相続対策は「感謝のカタチ」
相続とは、“誰がどれだけもらうか”ではなく、
“どのように次世代へ託すか”を考えるプロセスです。
そこに「感謝」と「思いやり」があれば、どんな家庭でもきっと良い形にまとまります。
FPとして私が伝えたいのは、「分ける」よりも「つなぐ」相続を。
そして、その第一歩を今日から始めてほしいということです。
そんな方は、まずは専門家との初回相談で現状を“見える化”してみましょう。
相続の不安は、感情ではなく仕組みで解消できます。
![]()
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP(FP上級資格)・証券外務員1種・宅地建物取引士・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員・不動産後見アドバイザー(全国住宅産業協会認定)・高齢者住まいアドバイザー(職業技能振興会認定) (独立系FP会社株式会社住まいと保険と資産管理 所属)」https://www.mylifenavi.net/





コメントフォーム